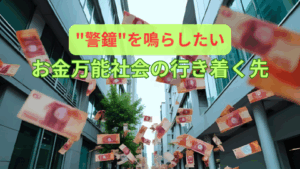経済至上主義が壊す民主主義
※政治に関する意見は極力控えてきましたが、最近の国政の状況や、それに端を発した社会情勢・世相を見渡すと、私見としての見解を発信することも必要ではないかと思うようになりました。今後は時折、そのようなテーマも取り上げていきたいと考えています。それも当団体の使命と判断いたしました。
「政治は誰のためにあるのか」という問いは、時代を超えて繰り返し投げかけられてきました。古代の都市国家から現代の議会制民主主義に至るまで、政治は本来「市民のためのもの」であると考えられてきました。ところが、現代社会を見渡すと、その理想と現実の乖離があまりにも大きいことに気づきます。政治の意思決定は、経済成長や企業利益を最優先する方向に偏り、市民の暮らしや福祉は後回しにされているのが実情です。この状況が続けば、民主主義そのものが「お金の論理」によって侵食され、形骸化していく危険性があります。今回は、経済至上主義が政治と民主主義をどのように歪めているのかを考え、その先にある社会の姿について問題提起したいと思います。

1 政治の本来の役割とは何か
政治とは、突き詰めれば「人々の暮らしをよりよくするための共同の仕組み」です。道路や教育、医療や福祉、治安や安全保障など、個人では担えない領域を社会全体で支えるのが政治の基本的役割です。そのために市民は税を納め、政治家を選び、政策の方向性を託してきました。
ところが現代では、政治の役割が「経済成長の推進」に矮小化されている感があります。GDPの数値が上がったか下がったかが、政治の成果を測る最大の物差しになり、人々の幸福や社会の安定といった本来の指標は脇に追いやられています。確かに経済の繁栄は重要です。しかし、それが唯一の目標となったとき、政治は市民を守るという本来の使命を見失ってしまうのです。

2 経済至上主義の構造
なぜ現代の政治は経済偏重になってしまったのでしょうか。その背景には複数の要因があると思います。
(1)グローバル競争の圧力
冷戦終結以降、世界は市場経済をベースにしたグローバル競争の時代に突入しました。資本は国境を越えて移動し、企業は安価な労働力や税制上の優遇措置を求めて拠点を移すようになりました。この結果、各国政府は「企業が逃げないように」規制緩和や減税を競い合い、結果的に企業の利益を優先せざるを得ない状況に追い込まれました。市民の暮らしや労働環境よりも、投資家の評価や株価の動向が政策決定に大きな影響を与えるようになったのです。
(2)選挙と資金の関係
民主主義国家における政治家は選挙で選ばれますが、その選挙には莫大な資金が必要です。広告宣伝費、スタッフの人件費、イベント開催費などを賄うため、政治家は必然的に企業や団体からの献金に頼らざるを得ません。資金提供者の意向が政策に反映されやすいのは当然であり、その構造そのものが「お金の論理」を政治に持ち込む大きな原因となっています。
(3)メディアと世論の形成
さらに問題を複雑にしているのは、メディアが経済の視点を強調しやすいという点です。株価の上下や景気の動向は数値で示しやすく、ニュースとして取り上げやすい反面、人々の幸福度や安心感といった指標は扱いにくい。こうして経済中心の言説が繰り返され、世論そのものが「経済がすべて」という意識に染まっていくのです。

3 犠牲にされる市民生活
経済至上主義の影響は、具体的にどのような形で市民生活に現れているのでしょうか。
(1)格差の拡大
まず顕著なのは格差の拡大です。企業利益を最優先にした政策は株主や経営層には恩恵をもたらしますが、労働者には必ずしも還元されません。非正規雇用の拡大や賃金停滞はその典型例です。結果として、一部の富裕層が資産を増やす一方で、多くの人々が生活苦にあえぐ状況が固定化されていきます。
(2)福祉や医療の後回し
財政赤字を理由に社会保障費が削減され、医療や介護の現場は慢性的な人手不足に陥っています。教育費の自己負担は重く、若者は奨学金という名の借金を背負って社会に出なければならない。こうした状況は、「経済成長を優先するから仕方ない」という論理で正当化されがちですが、まさに市民の暮らしを犠牲にして経済を守る発想に他なりません。
(3)環境問題の軽視と申しますか、一部の人のための推進。暗躍する政商。
地球温暖化や生態系の破壊といった深刻な環境問題も、短期的な経済利益の前には後回しにされることが多い。再生可能エネルギーへの転換や持続可能な社会への移行は長期的に不可欠であるにもかかわらず、「今すぐの経済成長」に縛られた政治は、抜本的な対策を打つことに消極的です。最悪なのはその領域においても利権構造が確立されてしまい、逮捕者までも出てしまう現状です。本末転倒の極みです。

4 民主主義の形骸化
経済至上主義の最大の問題は、民主主義そのものを形骸化させてしまう点にあります。市民の意思が政策に反映されるはずの仕組みが、実際には企業や資本の影響力に左右されてしまうのです。選挙で一票を投じても、その後の政治が「お金の力」によって動かされるなら、市民は無力感を抱き、政治への信頼を失っていきます。これは投票率の低下や政治的無関心となって表れ、民主主義の基盤を弱体化させます。
さらに、格差の拡大によって「声を上げられる市民」と「声を奪われる市民」の分断が進みます。資金や情報にアクセスできる層は政治への影響力を維持する一方で、生活に追われる層は政治参加の余裕を失い、結果的に「民主主義の主体」から排除されてしまうのです。

5 経済成長は本当に幸福をもたらすのか
ここで改めて問わなければならないのは、「経済成長は本当に人々を幸せにするのか」という点です。GDPが伸びても、格差が広がり、将来への安心が失われ、社会的孤立が深まるなら、それは果たして「豊かさ」と呼べるのでしょうか。
当団体においても度々話題にしましたが、幸福学やウェルビーイング研究では、一定水準以上の所得は幸福感に直結しないことが指摘されています。むしろ、人間関係の充実や安心できるコミュニティ、健康や自由といった要素こそが人々の幸福に直結することが明らかになっています。それにもかかわらず、政治は依然として経済成長を第一の目標に掲げ続けているのです。

6 「市民のための政治」への転換に向けて
では、どうすれば政治を「市民のためのもの」に取り戻すことができるのでしょうか。ここではいくつかの方向性を挙げます。
(1)多様な指標の導入
経済成長だけでなく、幸福度や健康寿命、社会的つながりといった指標を政策評価の基準に取り入れることが求められます。例えばブータンの国民総幸福量(GNH)や、OECDの「より良い暮らし指標(Better Life Index)」のような枠組みは、そのヒントになります。
(2)政治資金の透明化
選挙資金や政治献金の透明性を高めることで、企業や資本の影響力を弱め、市民の意思が反映されやすい仕組みに変える必要があります。市民による小口寄付の拡大や、クラウドファンディング的な仕組みの活用も一案です。

(3)市民参加の拡充
選挙だけに頼らず、熟議民主主義や市民会議といった仕組みを強化することが重要です。政策形成の過程に市民が直接関わることで、「自分たちの政治」という実感を取り戻すことができます。
(4)教育の役割
経済中心の価値観から解放されるためには、教育の役割も大きいと言えます。幸福や社会的責任、持続可能性といったテーマを学び、考える機会を増やすことで、将来を担う世代が「経済だけではない豊かさ」を理解できるようになるでしょう。

7 おわりに ―「誰のための政治か」を問い続ける
経済至上主義が支配する現代において、政治はしばしば「誰のためのものか」という本質的な問いを忘れがちです。しかし、その問いを忘れた瞬間、民主主義は形だけの制度へと変質し、市民は単なる経済の歯車にされてしまいます。
今こそ私たちは立ち止まり、問い直すべきです。「政治は企業のためのものなのか、それとも市民のためのものなのか」。答えは明らかであるはずです。政治は本来、市民一人ひとりの幸福と尊厳を守るために存在しています。その原点を取り戻さない限り、民主主義は経済の論理に呑み込まれ、空洞化していくでしょう。
未来の社会を形づくるのは、私たち一人ひとりの声と行動です。経済成長の数字に惑わされず、真に人間らしい暮らしを守る政治を求め続けること。それこそが、壊れゆく民主主義を立て直す唯一の道なのではないでしょうか。