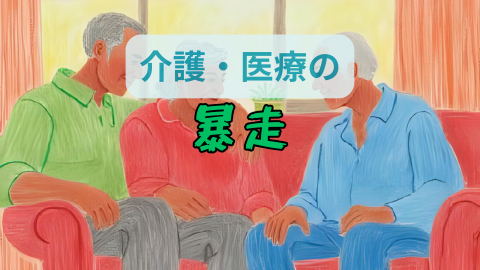
近年、介護現場で「ケアの暴走」とも呼ぶべき現象が問題視されつつあります。それは一見「手厚い支援」のように見えながら、実際には利用者本人の尊厳や意思を軽視し、自己満足的、または収益目的の側面を色濃く帯びたケアのことを指します。たとえば、本人の生活意欲や残存能力を削いでしまうような過剰な介助や、本来ならば本人の選択に委ねられるべき行動を、ケア側の都合で先回りして取り上げてしまう行為などです。
このような介護のあり方は、医療の世界における「医療の暴走」と本質的に通じています。必要性が薄いにもかかわらず行われる検査や処置、あるいはエビデンスの乏しい延命治療などは、患者本人のQOL(生活の質)を損ねることがあります。両者に共通しているのは、「ケアされる側」「医療を受ける側」の視点が失われ、提供する側の論理で動いてしまっているという点です。

「善意」と「業務」の境界線
介護者や医療従事者の多くは、善意や使命感を持って職務に従事しているはずです。しかし、制度の構造や現場の習慣の中に埋没していくうちに、「本当に必要なのか」「本人はどう思っているのか」という根本的な問いが置き去りにされてしまうことがあります。やがて、それは「とにかくやるべきことはやった」「マニュアルに従った」という、責任回避的なケアや医療に変質してしまうのです。
また、介護報酬制度や診療報酬制度により、ある種の行為が経済的インセンティブとして機能してしまう構造も見逃せません。制度の枠組みに則っていれば「合法」であるとしても、人間の生命や生活に直接関わる領域においては、「制度が正しい=行為が倫理的に正しい」とは限らないのです。

質の問題──国家に任せるための条件
現在、日本では高齢化が進み、介護も医療も国費によって多くが支えられています。つまり、国民全体の税金が投じられて、個々人のケアや治療が行われているということです。このように公的支援によって成り立つ制度だからこそ、担い手の「質」が厳しく問われなければなりません。
ここで言う「質」とは、単なる資格やスキルの有無にとどまりません。むしろ、「人間観」「倫理観」「他者への感受性」「自省する力」など、目に見えにくい部分が重要です。人を支える仕事は、その人の人生や価値観に踏み込むものでもあり、「正しさ」だけでは通用しない場面が多々あります。そのため、介護者や医師が自らの行為を省みる姿勢を持ち続けることが欠かせません。

では、どうすれば質は上がるのか?
まず、教育と研修の見直しが必要です。資格取得時の知識詰め込み型の試験ではなく、「対人関係力」や「倫理的判断力」などを評価対象に組み込む仕組みを整えるべきです。たとえば、介護福祉士や看護師の養成課程で、演習やグループディスカッションを通して、利用者の声を聞き取る訓練や自己の感情を省みる機会を設けることが有効です。
また、現場で働く人々に対しても、定期的な振り返りの機会や、感情を吐き出せるような場づくりが重要です。多忙で余裕がないからこそ、外部からのファシリテーションやスーパービジョンを導入し、「自分のケアは誰のためにあるのか」という原点に立ち返る機会が必要です。
さらに、利用者側の意識変容も欠かせません。「ケアは受けるものである」という受動的な感覚から、「自分の暮らしを自分で選ぶ」主体的な意識への転換を支援することが、暴走を止める鍵になります。たとえば、ACP(アドバンス・ケア・プランニング:人生会議)のような対話の機会を設けることで、「望ましいケア」「望まない医療」の線引きが事前に明確になるのです。

組織と制度も変わらねばならない
個人の意識改革と同時に、組織や制度の見直しも必要です。現在の制度は「量」を重視する傾向があり、「何をどれだけやったか」が評価の基準になりがちです。しかし、本来のケアや医療は「何をやらないか」「何を見守るか」という判断こそが重要なこともあります。そうした判断が「評価」に結びつかない限り、「暴走」は止まりません。
そのためには、「アウトカム評価」や「ナラティブ評価」の導入が考えられます。たとえば、ケア後に本人がどう感じたか、生活の満足度が上がったかといった主観的なデータも評価に反映させることで、「人間らしさ」に根ざした支援が見える化されます。
また、第三者によるチェック機能や倫理審査のような仕組みも併設することで、「やりすぎ」を未然に防ぐことが可能です。現場の声に耳を傾けつつ、国全体で支援の在り方を問い直す時期に来ているのではないでしょうか。

最後に──支援とは何かを問い直す
ケアや医療とは、「その人らしく生きること」を支える営みであるべきです。しかし今、「支援」の名のもとに人間性を奪ってしまうような事例が少なくありません。無意味なケアや医療が横行する背景には、制度の問題、経済的な問題、そして「支援する側の論理」が暴走してしまう心理構造があります。
今一度、「支援とは何か」「人間を支えるとはどういうことか」を、介護者・医療者・利用者・制度運営者のすべてが共有する必要があります。税金を使って任せる以上、質の担保は必須です。そして、その質は数値やマニュアルではなく、人と人の対話の中で育まれるものであることを、私たちは忘れてはなりません。

