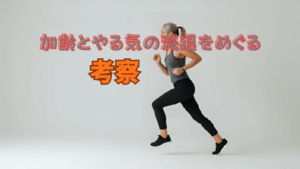この考え方をご存じでしょうか?いわゆる “0から1を生み出す” 発想と行動のこと を指します。
何もないところから新しい価値や仕組み、活動を生み出す力を意味し、ビジネスや社会活動、アート、研究などあらゆる分野で使われる言葉です。
起業や団体立ち上げなど、広範な分野で今注目されている『用語』です。
日本において「ゼロイチ人材」や「ゼロイチタイプ」といえば、
- 起業家
- 新規事業をつくる人
- NPO・コミュニティを立ち上げる人
- 新しい活動を社会に持ち込む人
など、「初期フェーズを作るのが得意な人」という意味で使われることが多いのですが、より厳密に言うと “立ち上げ行為” そのものよりも、“0から価値を生む思考と姿勢” を指す言葉です。
社会に必要な存在なんですが、既存の企業や組織にとってマイナス要素となる部分もありまして、なおかつ、持っている能力故の宿命的な事もあります。考えてみます。

■ゼロ1の人が組織で孤立しやすい理由
近年、「ゼロ1(ゼロワン)の人」という言葉を耳にする機会が増えてきました。ゼロをイチにする、つまり、まだ存在しないものを立ち上げることに長けた人を指します。概念やアイデアの段階にとどまっていたものを初めて社会の中に形として生み出す――その力は、起業家や新規事業担当者、または市民活動の立ち上げなど、あらゆる領域で重宝されます。一方で、ゼロ1の人は組織内で孤立しやすいという側面も持っています。むしろ、能力があるほど孤立が深まってしまうことすらあります。今回は、なぜゼロ1の人が組織で孤立しやすいのか、その心理的・社会的背景を紐解き、組織側がどのように支えるべきかについて考えていきたいと思います。
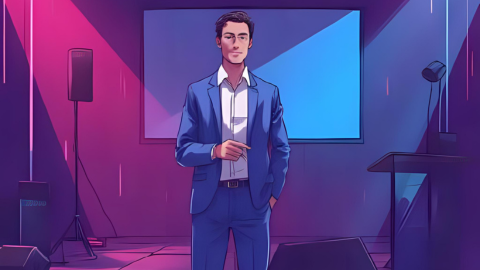
■1.ゼロ1とは何か(再度の説明)
ゼロ1の人とは、既存の枠組みやルールに縛られず、「まだ誰も手をつけていない領域」に踏み出し、そこに道をつくり、形をつくる人のことです。彼らは通常、三つの特徴を備えています。
- 直感的・構想力が強い
具体的な手順がなくても、ゴールイメージを思い浮かべることができます。 - リスク許容度が高い
周囲が不確実性を怖れる場面でも、前に進む勇気があります。 - エネルギーが高くスピードが速い
考える・動く・改善するのサイクルが非常に速く、他者が追いつけないこともあります。
こうした個性は創造性の源泉です。しかし同時に、組織との摩擦も生みます。組織は本来「1を10にする」「10を100にする」ことを得意としており、安定・再現性・規律を大切にします。ゼロ1の人はこの構造に根本的に適合しないため、双方のズレが孤立の原因となっていくのです。
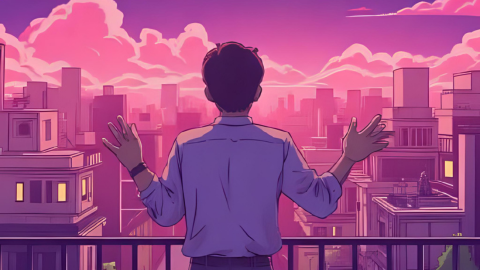
■2.ゼロ1型が孤立する心理的背景
ゼロ1の人が孤立する構造は、個人の性格や組織の体質だけではなく、人の心理にも深く関係しています。
①「理解されない」経験が蓄積しやすい
ゼロ1の人は未来のイメージを話すことが多いため、周囲からは「話が飛んでいる」「現実感がない」と受け止められることがあります。本人にとっては当然の連想や文脈であっても、周りにとっては接点が見えないため、理解・共感が得られにくいのです。
こうした経験が続くと、ゼロ1の人は「どうせ言っても伝わらない」と感じ、説明の労力をかけなくなる傾向があります。これがさらに溝を深め、一層コミュニケーションが減り、孤立が進んでいきます。
②批判や否定を受けやすい
ゼロ1のアイデアには「まだ形がない」という本質的な弱点があります。未知のものに対して、組織はしばしば懐疑的に反応します。
「それ、本当にできるの?」「今は忙しいからやめてほしい」「前例はあるの?」
こうした否定や慎重論は必ずしも悪意ではなく、組織を安定させたいという自然な反応です。しかし、これらの言葉を高い頻度で浴び続けると、ゼロ1の人は心が摩耗し、「自分は組織に歓迎されていない」と感じるようになります。
③スピードの違いが摩擦を生む
ゼロ1の人は、閃いた瞬間に動き始めることが多いです。しかし組織の動きは会議・稟議・根回し・承認プロセスなど、どうしてもゆっくりになります。その差が大きくなればなるほど、ゼロ1の人は「遅い」「どうして動かないのか」と不満を抱き、逆に組織側は「勝手に動く」「調整ができない」と不信感を抱きます。
この「速度差による摩擦」はとても深刻で、両者の不一致は互いの孤立感をさらに強めていきます。

■3.組織構造がゼロ1の人を孤立させる理由
ゼロ1は、その性質ゆえに組織構造と相性が悪い部分があります。
①組織は「最適化の仕組み」で動いている
多くの組織では、効率・再現性・手順化・分業化が重要視されます。新しいものを立ち上げる活動は手間もコストもかかり、結果も保証されません。つまり組織にとって「ゼロ1」は合理的な優先順位から外れやすいのです。
②評価制度が合っていない
評価基準が「成果」「成果物」「プロセスの管理」に置かれている組織では、形になる前のゼロ1活動はどうしても評価されません。
ゼロ1の人は見えにくい創造的作業に多くの時間とエネルギーを使いますが、評価されず、周囲にも理解されず、結果的に疎外感を抱くことになります。
③同調圧力との相性が悪い
日本の組織文化では「空気を読む」「和を乱さない」ことが強く求められます。一方で、ゼロ1の人は空気よりも未来を見ています。今ここにある空気より、将来の価値の実現を優先します。
その結果、組織の中では「変わった人」「少し浮いている人」という認識を持たれやすく、相談相手も減ってしまいます。

■4.孤立がもたらす影響
ゼロ1の人が孤立すると、個人・組織双方にさまざまな影響が出ます。
- 本人のモチベーション低下
孤立は精神的負荷となり、創造性の低下につながります。 - 離職・独立の増加
組織の理解が得られない場合、ゼロ1の人は環境を変えることで自分の力を発揮しようとします。 - 組織の停滞
ゼロ1型の創造性は、本来組織に新風をもたらす貴重な資源です。それが活用されないことは、組織にとって大きな損失になります。

■5.ゼロ1の人を孤立させないために
では、組織はどのようにゼロ1の人を支援すればよいのでしょうか。
①「翻訳者」を置く
ゼロ1と組織の間には言語のギャップがあります。未来志向の言葉を、組織が理解できるロジックに変換する「橋渡し役」が必要です。この存在がいるだけで摩擦は大幅に減少します。
②小さな実験の仕組みを導入する
いきなり大きなプロジェクトとして扱うのではなく、「まずは小さなテスト」を許可することで、ゼロ1の人は試す自由を得られ、組織はリスクを抑えることができます。

③評価軸を増やす
プロセス評価、創造性評価、挑戦評価など、成果以外の評価軸があることで、ゼロ1の人は「理解されている」と感じやすくなります。
④心理的安全性の担保
アイデアを発言しても嘲笑されない、否定ではなく質問が返ってくる環境づくりが大切です。孤立の多くは、場の空気から生まれます。
■6.おわりに
ゼロ1の人は、組織にとって「未来をつくる力」です。しかし、その力は理解されなければ孤立し、失われてしまいます。組織は安定性を、ゼロ1の人は創造性を、それぞれ役割として持っているにすぎません。どちらかが優れているのではなく、両者の違いを認識し、協働できる仕組みを整えることが重要なのです。
ゼロ1の人が活躍できる組織は、常に変化に対応し、新しい価値を生み続ける組織です。孤立を防ぐことは、単なる個人のケアにとどまらず、組織全体の未来を開く取り組みでもあります。

これからの社会において、ゼロ1の人材はますます重要になるでしょう。彼らが孤立せず、本来の能力を発揮できる環境づくりこそ、組織が持続的に成長するための鍵となるのではないでしょうか。