
~親の認知バイアスに向き合う~
1. はじめに ― 心理の奥底にある「親心」
「うちの子に限って、そんなことをするはずがない。」
この言葉は、ニュースや学校現場、家庭の会話の中で繰り返し耳にするフレーズです。多くの場合、親が自分の子どもを信じたい気持ちから自然に出てくるものです。親にとって我が子は、日々の生活を共にし、笑顔や努力の姿を間近で見てきた存在です。そのため、外部から「問題行動」や「トラブル」について指摘を受けても、直感的に否定してしまうのは、ある意味で人間らしい反応と言えるでしょう。
しかし、この「うちの子に限って…」という思い込みは、ときに“親の認知バイアス”として働き、重大な問題の発見を遅らせたり、子どもへの適切なサポートを阻む要因になります。この心理メカニズムを紐解き、そのリスクと向き合い方について考えていきます。今回も投稿者の経験が反映されています。
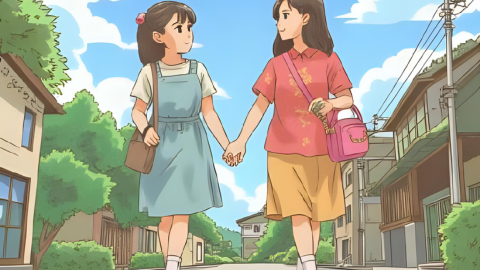
2. 親の認知バイアスとは何か
認知バイアスとは、人が物事を判断するときに、無意識に偏った見方や誤った結論に至ってしまう心理的傾向を指します。親子関係においては、次のようなバイアスが特に強く作用します。
- 確証バイアス(Confirmation Bias)
人は自分が信じたい情報や期待する情報ばかりを集め、それに反する情報を無視または軽視する傾向があります。例えば、先生から「お子さんが授業中に何度も注意を受けています」と言われても、「うちの子は家では大人しいから、きっと何かの誤解だ」と考えやすくなります。 - 感情バイアス(Affect Bias)
愛情や信頼感といった感情が判断に影響を与えることで、客観的な事実を直視できなくなります。子どもを守りたいという気持ちは自然ですが、それが現実認識を曇らせることがあります。 - 自己防衛バイアス(Self-serving Bias)
「もし子どもが悪いことをしていたら、それは自分の育て方が悪かったことになる」という無意識の自己防衛が働きます。結果として、問題の存在自体を否定してしまうのです。

3. 「うちの子に限って」が引き起こすリスク
(1) 問題の早期発見の遅れ
いじめ、非行、依存症、ネットトラブルなど、子どもが巻き込まれるリスクは多岐にわたります。親が「そんなはずはない」と信じ込むことで、初期のサインを見逃し、事態が深刻化してから発覚するケースは少なくありません。
(2) 子どもへの誤ったメッセージ
もし子どもが実際に問題行動を起こしていた場合、親がそれを否定し続けることは、「自分は許される」という誤解を与えます。反省や改善の機会が失われ、同じ行動を繰り返すリスクが高まります。
(3) 周囲との信頼関係の崩壊
学校や友人の親、地域社会からの指摘に耳を貸さない姿勢は、やがて周囲との信頼関係を損ないます。問題が発覚したとき、協力して解決にあたるためのネットワークが断たれてしまう恐れがあります。

4. なぜ人は「信じたい現実」に固執するのか
人間の脳は、不快な情報や自己像を脅かす事実を避ける傾向があります。心理学者レオン・フェスティンガーが提唱した認知的不協和理論によれば、人は自分の信念や価値観と矛盾する情報に接すると、不快感(不協和)を覚え、それを解消しようとします。このとき、多くの人は事実を修正するよりも「情報を否定する」「自分に都合よく解釈する」方向に動きます。
親子関係の場合、「子どもは良い子である」「私は良い親である」という自己イメージが非常に強いため、それに反する現実を受け入れるのは心理的に痛みを伴います。結果として、「うちの子に限って」という幻想にしがみついてしまうのです。

5. 事例で見る「幻想」の影響
事例1:いじめ加害の否認
中学生のA君は、学校で特定の同級生をからかう行為を繰り返していました。担任は複数回保護者に連絡をしましたが、母親は「家では優しい子ですし、友達思いですから、そんなことをするはずがない」と一貫して否定。結果として対応が遅れ、被害者の不登校が長期化しました。
事例2:ネット依存の見逃し
高校生のBさんは、夜遅くまでスマホを使い、睡眠不足から学校での成績が低下。担任が保護者面談で指摘しましたが、父親は「うちの子は勉強も部活も頑張っている。スマホは息抜きに使っているだけ」と受け入れませんでした。その後、依存が進み、生活リズムの崩壊により体調不良が慢性化しました。

6. 幻想から抜け出すための視点
(1) 「あり得るかもしれない」という仮説思考
まずは「うちの子にも問題行動があり得る」という仮説を持つことが大切です。これは疑うことではなく、あくまで事実確認のための出発点です。
(2) 第三者の視点を借りる
学校の先生、スクールカウンセラー、医師、地域の支援員など、親子以外の視点を積極的に取り入れることで、認知バイアスを和らげることができます。
(3) 子どもとの日常的な対話
日々の会話の中で、表情や口調の変化、言葉の選び方に敏感になることで、早期に違和感を察知できます。「最近どう?」と聞くだけではなく、「今日は何が一番楽しかった?」など具体的な質問が効果的です。
(4) 親自身の価値観の柔軟化
「良い子であること」や「成功すること」だけが子どもの評価基準ではないと理解し、行動の背景や心の状態に目を向ける習慣を持ちましょう。

7. まとめ ― 信じることと見守ることの違い
「信じる」ということは、単に良い部分だけを見て肯定することではありません。信頼とは、事実を受け止め、そのうえで支え続ける覚悟を伴うものです。「うちの子に限って…」という幻想を手放すことは、親としての愛情を否定することではなく、むしろ真の意味で子どもを守る行為です。
現実を直視することは時に苦しいものですが、その一歩が、子どもが自分の行動を見つめ直し、成長するための土台となります。そして、その成長の過程を支えられるのは、やはり親の存在にほかなりません。

