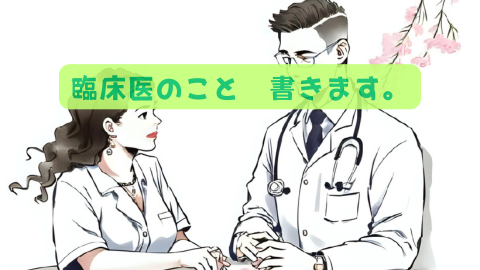
臨床医の使命と現代社会における葛藤
近年、医療現場における変化や課題が顕在化する中で、「臨床医とは何のために存在しているのか」という根本的な問いを多くの人が抱くようになっています。かつて医師という職業は、神聖さと崇高さを象徴する存在でした。病める人に寄り添い、命と健康を守ることが医師の使命であるという共通認識がありました。実際はどうあれ、少なくとも私はその様に思っていました。しかし現代社会においては、医師の姿が「社会的成功者」「高収入層」「医療ビジネスの担い手」といった異なる側面で語られることが増え、使命感よりも利益追求が前面に出ているように見受けられる場面も少なくありません。

このような現象の背景には、医療が経済活動の一部に組み込まれてしまった構造的問題が存在します。医療機関も企業と同様に、経営を維持するためには利益を確保する必要があります。設備投資、人件費、地域貢献、研究開発など、あらゆる支出に対し安定した収入が求められる中で、医師個人もまた経済的な責任を担う立場に置かれているのです。

本来、臨床医の使命とは何でしょうか。臨床とは「ベッドサイド」での診療を意味し、患者の痛みや苦しみに直接触れ、診察・治療・看取りを通じて、その人の人生に寄り添う営みです。診断技術や治療法がいかに進歩しても、患者が安心し、信頼して身を預けられる医師の存在は不可欠です。医師の仕事の本質は、人間の苦悩を共有し、癒しに導くプロフェッショナルであることにあります。

しかし、現代ではその理想と現実の間に大きな乖離が生じています。たとえば、患者を「顧客」とみなす風潮や、「収益性の高い診療科」への偏重、あるいは「保険点数のための治療」といった現場での選択は、医師の価値観を徐々に変容させているように思えます。特に自由診療領域では、より収益を上げやすい美容医療などに医師が流れていく傾向が強まり、重篤な慢性疾患や終末期医療などの報酬が低く評価される領域が人手不足になるという、皮肉な現象も生まれています。
また、SNSやメディアの影響も見逃せません。最近では、医師が「インフルエンサー化」し、フォロワー数やビジネス展開に注目が集まることも多くなっています。もちろん、医療情報の発信や啓発活動自体は意義あるものですが、その裏に「自己ブランド化」や「収益モデル化」が見え隠れするようになると、本来の医師の在り方とは距離を感じざるを得ません。

こうした状況を見るにつけ、「お金があるのに、なぜさらに求めるのか」という疑問が浮かびます。欲望は本来、人間に備わった自然な感情ではありますが、それがコントロールを失い、過度な自己利益の追求へと傾いた時、周囲との信頼関係を損ねることになります。医療においてその信頼は生命線とも言えるものであり、そこに陰りが見えると、患者と医師の関係は不安定になってしまいます。

しかし、全ての医師がこうした価値観に染まっているわけではありません。今もなお、使命感と倫理観を持ち、患者のために誠実に向き合っている多くの臨床医が存在します。彼らは、効率や収益よりも、人間としてのつながりや、治療の意味そのものを大切にし、時には組織の意向に逆らってでも患者の利益を優先しています。そうした姿勢が今、より一層貴重で尊いものとして光を放っています。
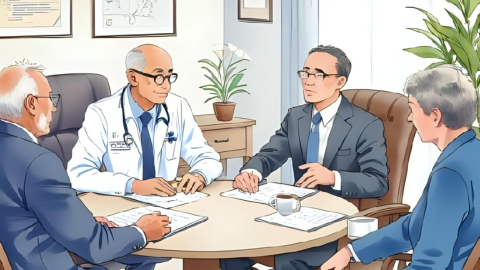
臨床医に求められるのは、まず第一に「他者の苦しみを自分ごととして感じる感性」であり、そのうえで「何が最もその人のためになるのか」を考え、実行する実践力です。そしてもう一つ、現代においては「誘惑に流されない倫理性」も大きな要素となってきています。どんなに制度が不完全でも、どれほど収益重視の圧力が強くても、自らの信念を持って医療に向き合う覚悟こそが、真の医療者の条件なのかもしれません。

今後の医療を考える上では、こうした本質的な問いを私たち社会全体が改めて見つめ直すことが必要です。患者側も医師に対し「サービス提供者」としての期待だけでなく、「人間としての弱さ」や「職業倫理の重さ」に目を向け、医師とともに信頼の医療関係を築いていく努力が求められます。

臨床医の使命は、お金や名声を得ることではなく、「人の命に向き合い、その尊厳を支えること」に他なりません。それを見失わずに歩み続けることができる社会の仕組みこそ、私たちが今、本気で取り組むべき課題なのではないでしょうか。その様に私は思います。

