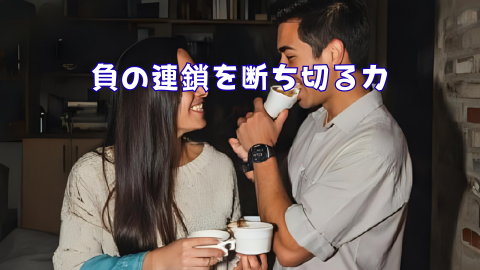
家庭という小さな社会が未来を決める
私たちは皆、ある環境の中で育ちます。
その環境は、愛情に満ちていたかもしれませんし、そうでなかったかもしれません。
しかし共通して言えるのは、「幼少期に受けた環境や関わり方が、その後の人生に深く影響を与える」という事実です。
心理学的にも、脳科学的にも、幼少期の体験は人格形成や人間関係の築き方、さらには自己肯定感の基盤に大きく関わることが明らかになっています。

■ 無意識の中に刻まれる“家庭の記憶”
人は成長する中で、「自分の家庭が普通」だと信じて生きています。
親の言動、夫婦の関係、兄弟との関わり――それらは、子どもにとって“世界の縮図”です。
だからこそ、たとえ虐待や暴力、無関心や言葉の暴力の中で育っても、それが「家庭というもの」だと刷り込まれてしまうのです。
成長し、やがて自分が親となったときに、無意識のうちに同じ行動を繰り返してしまう。
「自分は親とは違う」と心に誓っていたとしても、ストレスや疲労、孤独が重なった瞬間に、かつての親の口調や態度が、自分の中から不意に顔を出す。
そのとき人は、愕然とするのです。
「あれほど嫌だった自分の親と、同じことをしてしまった」と。
この“無意識の継承”こそが、負の連鎖の厄介な部分です。
知識や理性ではなく、感情と反応のレベルで受け継がれてしまう。
それは、「愛し方を知らないまま、大人になってしまう」ことの悲劇でもあります。

■ 若年出産と孤立の現実
近年、ニュースで目にする虐待事件の中には、「家庭に事情があり、若くして母親になったケース」が少なくありません。
貧困やDV、家庭崩壊など、本人の努力ではどうにもならない環境が背景にあることも多い。
幼い頃から十分な愛情を受けられずに育った人が、若くして母親になり、心の余裕を持てないまま子育てに追われる。
そこに頼れる人もいなければ、支えの仕組みも十分でない。
そんな中で、再婚相手が子どもに手を上げても、「どうして止められなかったのか」と責めるのは、あまりに酷かもしれません。
防衛する気力も、判断する力も奪われている場合があるのです。
暴力の中で生きてきた人にとって、それが「異常だ」と感じるセンサーが鈍ってしまっていることもあります。
これは決して個人の弱さではなく、社会が見過ごしてきた“孤立”の問題なのです。

■ 愛情の欠如がもたらす「感情の貧困」
虐待や放任の家庭に育つと、子どもは“感情の学習”を十分に行えません。
人の痛みを想像する力――共感力――は、家庭内での安心した関係の中で培われるものです。
抱きしめられた経験、受け止められた記憶が、「他者も同じように大切にしていい存在だ」という感覚を育てます。
その基礎が欠けたまま大人になってしまうと、人との距離感をうまく取れず、過剰に依存したり、逆に心を閉ざしてしまったりすることがあります。
それは単に“情緒不安定”という言葉で片づけられる問題ではなく、社会全体が育むべき「人間の感情の豊かさ」が失われていく危険でもあります。
愛情を知らないまま生きるということは、人生の土台が揺らいだまま家を建てるようなものなのです。

■ 「気づく」ことからしか連鎖は止まらない
では、どうすればこの負の連鎖を断ち切ることができるのでしょうか。
答えは、一つではありません。
ただ、共通して言えるのは――“自分が受けてきた影響を自覚すること”です。
多くの人は、自分の家庭を振り返ることを避けます。
痛みを伴う記憶だからです。
しかし、「あの時のあの言葉が、自分の価値観を縛っていたのかもしれない」と気づくこと。
「親も不器用な愛し方しかできなかった」と理解し直すこと。
そこからしか、変化は始まりません。
人は、気づいた瞬間から“選ぶ自由”を取り戻します。
過去に支配されるのではなく、「ここで断ち切る」という意志を持てるようになる。
その意識の芽が、次の世代への新しい伝達を生むのです。

■ 支える社会の仕組みを
個人の努力だけでは、限界もあります。
だからこそ、社会として“支える構造”が必要です。
孤立した母親が安心して相談できる場、再婚家庭での子どもの安全確認を徹底する制度、そして何より「助けを求めてもいい」という文化の定着。
日本社会では、いまだに“家庭のことは家庭で”という空気が根強く、外部の介入を嫌う傾向があります。
しかし、その沈黙の中で、どれだけの子どもが救われずにいるのでしょうか。
児童相談所や自治体の支援体制が形だけで終わらないためには、現場の職員が声を上げやすい環境、そして地域社会全体で“気づく力”を高める教育が欠かせません。
虐待防止は、行政の責任であると同時に、私たち一人ひとりの意識の問題でもあるのです。

■ 「親になる」ということの本当の意味
親になるということは、ただ命を育てることではありません。
自分の中にある“過去”と向き合い、それを子に渡さない努力をすることです。
自分が受け取れなかった愛を、次の世代には渡そうとする――それは簡単なことではありません。
しかし、その努力こそが、人間の強さであり、希望です。
子どもにとって、完璧な親である必要はありません。
間違いながらも謝れること、気持ちを伝えようとすること、そして子どもを「一人の人間」として尊重すること。
それが、次の世代に“健全な心の土台”を残す最も確かな方法です。

■ 未来へ ― “連鎖”から“継承”へ
家庭という場所は、人を傷つけもすれば、人を救うこともできます。
負の連鎖を断ち切った先に待っているのは、新しい“継承”です。
愛情の受け渡し、思いやりの循環――それは誰かの「勇気ある選択」から始まります。
どんなに小さな気づきでも構いません。
「あの時の自分のような子を、今度は守りたい」
そう思えた瞬間から、人は変わります。
そして、その変化が次の命を救うのです。
家庭の中で生まれる悲劇は、社会の中でしか防げません。
「見て見ぬふりをしない」という意識の広がりが、子どもたちの未来を守る力になります。
私たち一人ひとりが、“気づきの担い手”になる。
それが、負の連鎖を断ち切るための第一歩と重いんす。

