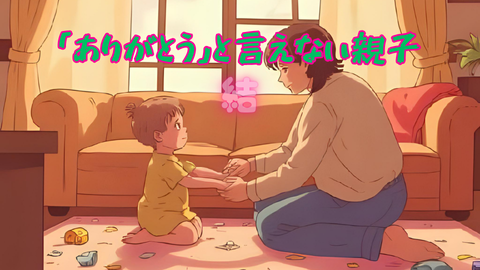
感謝が伝わらない理由とは?
私たちは、「親子だからわかり合える」と思いがちです。しかし、実際には、最も身近な存在であるからこそ、素直な言葉を伝えることが難しくなるという矛盾を抱えています。その象徴ともいえるのが、「ありがとう」という言葉。日常的に何気なく口にするこの一言が、親子のあいだでは驚くほど言えなかったり、伝わらなかったりすることがあります。
今回の投稿では、「ありがとう」と言えない親子の背景にある感情や世代間の価値観、そして感謝が伝わらないすれ違いの構造について考察しながら、その意味を改めて問い直してみたいと思います。あくまでも小生の経験を基にしています。

1. 言葉にしなくても伝わる?―親世代の価値観
昭和から平成初期に育った親世代には、「感謝は態度で示すもの」「言葉にしなくても気持ちは伝わる」という価値観が根づいています。特に父親世代には、「照れくささ」や「口数が少ないことこそ誠実」とする美学があり、家庭内で感情を言語化する習慣が乏しかった傾向があります。まぁ、美学とまではいきませんが、、。
たとえば、父親が仕事から帰宅し、「今日も一日お疲れさま」と子どもに声をかけられる光景は、日本の家庭ではあまり一般的ではありません。子どももまた、親に対して「ごはんありがとう」「毎日働いてくれてありがとう」とは言いにくい環境で育つことになります。
親がしてくれたことは、当たり前として受け取られがちで、それに対してわざわざ感謝の言葉をかけるという文化が希薄だったのです。

2. 感謝の表現を学ばなかった子ども世代
一方、子ども世代、特に令和を生きる若者たちは、SNSや学校教育の中で「感謝を言葉にしよう」「思いをちゃんと伝えることが大事」という価値観に触れる機会が多くなりました。そのため、相手からの「ありがとう」を期待する気持ちが強くなる傾向があります。
ところが、親から感謝の言葉をもらったことが少ない場合、「自分は感謝されていない」「大切に思われていない」と感じてしまうことがあります。同時に、子ども自身も、感謝の言葉をどのように親に向けて発すればいいのかわからないまま大人になってしまうことも少なくありません。
つまり、親の無言の価値観と、子どもの言葉を求める気持ちとのあいだで、すれ違いが生じているのです。

3. 「してくれて当然」という感情の壁
親は子どもに対して無償の愛情を注ぎ、育ててきました。ところが、その「無償」であるがゆえに、感謝されることを期待してはいけない、という考えに縛られてしまうことがあります。一方で、どこかで「少しくらい『ありがとう』と言ってほしい」と感じているのも本音でしょう。
子どももまた、「親は自分に尽くして当然」と思い込んでしまうことがあります。食事の準備、洗濯、送り迎え、進学や就職の支援――それらがあまりに日常に溶け込んでいるために、それが「労力」であることを認識できず、感謝の対象として見えにくくなるのです。
親の側も、「あんなにしてやったのに、ひと言もない」という不満を持ちながらも、それを口に出さないため、感情の蓄積が起こり、関係がぎくしゃくしてしまうこともあります。

4. 「ありがとう」が言えないのは不仲だからではない
「親に感謝できないのは、親子関係が悪いからだ」と思われがちですが、実際には、関係性が深いほどに、感謝の言葉が言いにくくなることがあります。そこには、「今さら照れくさい」「言ったら負けた気がする」「うまく言えない」という、複雑な感情が交錯しているのです。
特に、思春期や若者に多いのが、「ありがとう」と言うことで、自分が弱くなったような気がするという心理です。親のありがたさを認めることで、自立しきれていない自分を突きつけられるように感じてしまうのです。
また、親の側も、「今さら『ありがとう』と言われても受け止め方がわからない」と感じる場合があります。長年言葉を交わさずにきたからこそ、突然の感謝の言葉に戸惑い、素直に受け取れない――そんな場面も少なくありません。

5. 感謝は“言葉”よりも“存在”に宿る
とはいえ、「ありがとう」と言えないからといって、親子の関係が壊れているわけではありません。むしろ、言葉にならない感情が深く流れていることの表れともいえます。
たとえば、何気ない日常のやり取り、手料理に込めた心、病気のときの看病、朝晩の送り迎え――そこには多くの“ありがとう”が隠れています。言葉にはならなくても、互いの存在そのものが感謝でつながっているというケースも多いのです。
しかし、人はときに、言葉にしないと伝わらない、という局面にぶつかります。だからこそ、ほんの一言の「ありがとう」が、長年のすれ違いや誤解を溶かす力を持つのです。

6. 小さな「ありがとう」から始めよう
親子のあいだに流れる長い時間は、ときに言葉を硬直させます。しかし、それを少しずつほぐすことは可能です。
「今日はおいしかったよ」「寒いのに迎えに来てくれて助かった」「心配してくれてありがとう」――そんな小さな一言から始めることで、親も子も心の鎧を少しずつ脱いでいけるかもしれません。
特に、高齢になった親にとっては、子どもからの「ありがとう」は心に深く沁みわたります。遅すぎるということはありません。関係を修復しようと意気込まずとも、「ありがとう」をひとつ置くだけで、関係は少しずつ柔らかくなっていくものです。

主観的な意見の、おわりに
「ありがとう」と言えない親子には、それぞれの歴史や価値観、感情の積み重ねがあります。しかし、それは「分かり合えない」という壁ではなく、「分かり合いたいけれど、不器用なだけ」という距離でもあるのです。
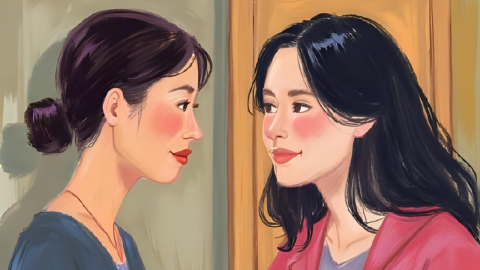
感謝を言葉にすることは、決して派手な行為ではありません。けれど、そこには人生をしなやかに結ぶ力があります。親だから、子だからと構えずに、まずは自分から一歩踏み出す――その勇気が、これまで伝わらなかった思いを動かし始めるきっかけになるのかもしれません。

