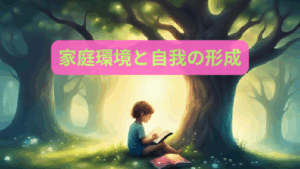自分の心の問題→他人を巻き込んで処理してしまう人たち
――経験から学び、少し勉強してみた!――
私たちは日々、いろいろな人と関わりながら生きています。家族、職場の同僚、友人、ご近所さん…。その中には、なぜか「いつもトラブルの中心にいる人」や、「話すとどっと疲れる人」がいることはありませんか? よくよく見てみると、そうした人は、自分の中の不安や怒り、満たされない思いを、まるで他人に「ぶつける」かのように表現していることが多いのです。
このように、自分の心の問題を、他人を巻き込むことで処理しようとする人がいます。それは無意識のうちに行われていることがほとんどで、本人は悪気がない場合も多いのが特徴の様です。今回は、このような人の心理的背景について、実際の事例を交えながら、やさしく学んでいきたいと思います。

■ 事例1:怒りっぽい上司の正体
たとえば職場にこんな上司がいたとします。
「小さなミスにも異常に怒る」「部下のやることすべてに文句を言う」「誰かが辞めると、次のターゲットが現れる」
このような人は、実は自分の中に「自信のなさ」や「劣等感」を抱えていることがあります。それを自分で認めるのが怖いため、他人のミスや欠点をあげつらうことで、相対的に「自分は上」と感じようとしています。
心理学では、こうした行動を「投影(projection)」や「攻撃的外在化(externalization)」と呼びます。自分が心の中で感じている不快な感情や不安を、自分の外にある誰かに押しつけることで、一時的に安心しようとしているのです。

■ 事例2:被害者を演じて、周囲を動かす人
ある女性が友人関係で孤立してしまい、こんな言動を繰り返すようになりました。
「私ばかり誘われないのは、みんなが私を嫌ってるからよ」
「どうせ私はひとりぼっち、みんな冷たい」
「助けてくれないあなたも、同じよ」
最初は同情して手を差し伸べた友人たちも、次第に疲弊し、距離を置くようになります。しかし当の本人は、「また裏切られた」と思い込み、自分の中の不安をさらに増幅させてしまうのです。
このようなケースでは「被害者意識を通じて他人をコントロールしようとする心理」が働いています。無意識のうちに、他人を「悪者」に設定することで、自分の孤独や不安を正当化しているのです。

■ なぜ「他人を巻き込む」ようなことが起きるのか?
こうした行動の背景には、大きく2つの心理的要因があります。
① 自分の気持ちを整理できない
人は誰しも、ストレスや不安を抱えると、それを「どうにかして消化したい」と思います。けれども、言葉で整理したり、自分で気づいたりする力が弱いと、その不安はうまく処理されず、心の中でどんどん膨れ上がります。結果として、「他人にぶつける」「他人に察してもらう」「他人を操作して安心を得る」といった行動に出てしまうのです。
② 愛情や安心感を、ゆがんだ形で求めている
「怒ることで相手を動かす」「悲劇のヒロインとして振る舞う」――これは、一見するとネガティブな行動ですが、裏には「もっと自分を大事にしてほしい」「わかってほしい」という、切ない欲求が隠れています。けれども、素直に「助けて」と言えないため、ゆがんだかたちで他人を巻き込んでしまうのです。

■ 境界性パーソナリティ傾向との関連
このような行動は、ときに「境界性パーソナリティ傾向(BPD)」と呼ばれる特性の一部として語られることもあります。BPDの人は、対人関係において極端な不安や依存を感じやすく、「好き」と「嫌い」が激しく入れ替わったり、「見捨てられるのでは」という恐怖から相手を試すような行動に出たりすることがあります。
もちろん、こうした傾向があるからといって「病気」と決めつける必要はありませんが、慢性的に他人との関係でトラブルが起こる場合には、一度、心理的な相談機関にかかることも一つの方法です。

■ どう対応する? 巻き込まれないために
このような人と関わるとき、最も大切なことは「自分まで巻き込まれすぎない」ことです。いくつかの対応のヒントをご紹介します。
● 境界線を引く(心理的な距離を保つ)
「ここからはあなたの問題」「ここからは私の問題」と意識するだけでも、気持ちの負担が軽くなります。たとえば、感情的に訴えられたときに「それはあなたの気持ちなのですね」と、相手の話を受け止めつつ、自分が背負い込まない姿勢を見せることが有効です。
● 無理に解決しようとしない
「どうにかしてあげなきゃ」と思って行動すればするほど、相手はその関係に依存してしまうことがあります。ときには「自分で考えてみたらどうかな?」と、相手自身にゆだねる姿勢も大切です。

● 信頼できる人に相談する
特に家族や職場など、長く関わらざるを得ない場合には、自分だけで抱え込まず、第三者の助けを借りることが大事です。場合によっては、専門のカウンセラーや精神保健の相談機関に相談することで、より良い距離感を築くヒントが得られることもあります。
■ 誰もが「巻き込んでしまう」可能性がある
「他人を巻き込んで心を処理する人」は、決して特別な存在ではありません。ストレスが溜まっているとき、自分に余裕がないとき、人は誰でも似たような行動を取ってしまう可能性があります。だからこそ、「自分の内面と向き合うこと」「人との間に健全な距離を持つこと」「ときには誰かの助けを借りること」が、とても大切なのです。
他人に巻き込まれないようにしながら、同時に相手の心の奥にある「助けて」というサインにも気づけるような、やさしい目線を持てるといいですね。