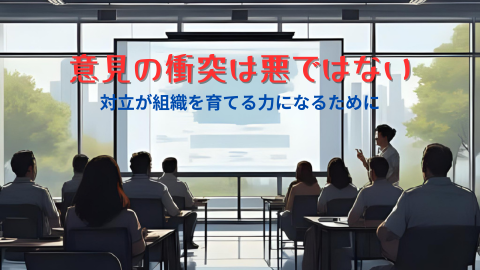
対立が組織を育てる力になるために・・・
組織の中で、意見がぶつかる場面ほど気まずいものはありません。会議の空気が一瞬で張り詰め、沈黙が場を支配する。誰かが強く主張をすれば、別の誰かがそれを「攻撃」と受け取ってしまう。日本の組織文化では、意見の衝突を“避けるべきこと”として扱う傾向がいまだ根強くあります。
しかし、本当にそれで組織は前に進めるのでしょうか。
意見が異なるというのは、見方が違うということです。見方が違うということは、そこに新しい発想や気づきの可能性があるということでもあります。もし組織が一枚岩でしかなく、誰も異を唱えないとすれば、それは“調和”ではなく“停滞”に近い状態です。対立は不快なものかもしれませんが、それを避けることが常に正しいとは限りません。むしろ、意見の衝突をどう扱うかこそが、組織の成熟度を測る指標になるのではないでしょうか。
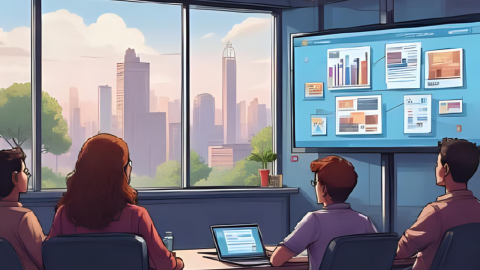
■ 「正しさ」を競うと、組織は壊れる
対立が生じたとき、私たちはつい「どちらが正しいか」を判断しようとします。ですが、問題は多くの場合、正誤の問題ではなく、価値の優先順位の違いにあります。
たとえば、ある人は「スピード」を重視し、別の人は「丁寧さ」を大切にする。どちらも正しい。けれど、場面によって求められるバランスが異なるだけのことです。にもかかわらず、「あなたのやり方は間違っている」と言ってしまえば、建設的な議論は途端に感情のぶつかり合いに変わります。
実際、多くの組織で見られるのは、「正しさ」の名のもとに他者を封じ込める風潮です。
それは、個々の意見が尊重されていないことの表れでもあります。
本来、組織とは目的を共有しながらも、多様な価値観を内包する“生き物”のような存在です。その中で、「全員が同じ考えでなければならない」と考えるのは、生命にとっての多様性を否定するのと同じです。
「異なること」を受け入れる器量が、組織をしなやかにします。
つまり、対立を排除するのではなく、“健全な衝突”として活かす仕組みが必要なのです。

■ 対立が生まれるのは「理念が生きている証」
組織における理念や目的は、固定された“標語”ではありません。
社会の変化、人々の意識の変化にあわせて、常に見直され、磨かれていくべきものです。ところが、多くの組織では理念が“お飾り化”し、日々の現場と乖離していくケースが見られます。
この乖離を埋める力になるのが、実は「意見の衝突」なのです。
現場で働く人が「今のやり方は現実に合っていない」と声を上げたとき、そこには理念を“生きた形”に更新しようとするエネルギーがあります。対立が起きるのは、理念が死んでいない証拠。もし誰も疑問を持たず、すべてが穏便に進んでいるように見えるなら、それは組織が“思考停止”に陥っているサインかもしれません。
理念を「守ること」ばかりに目を向けると、組織は硬直します。
一方で、理念を「進化させるための対話」が行われる組織は、時代に応じて柔軟に形を変えていきます。
つまり、衝突は“理念の再生装置”のようなものなのです。

■ “調和”よりも“対話”を重んじるということ
日本社会では、長らく「和をもって貴しとなす」という価値観が重んじられてきました。
確かにそれは、人間関係を円滑にし、無用な争いを防ぐ知恵でもあります。
しかし、その「和」が「沈黙の同調」へと変質してしまうとき、問題が生じます。
たとえば、会議の場で誰も反対意見を言わない。
言えば“空気を読めない人”と見られる。
そうして生まれた結論は、表面的には穏やかでも、内実は誰も納得していない“虚ろな合意”にすぎません。
“調和”を保つために“対話”を犠牲にする。
その反面、そういう組織は犠牲に比例して表面化しないところで"異論"がエスカレートします。
それは、組織にとって大きな損失であり、常習化すると組織の体質にもなり得る危険な信号です。
本来の「和」は、異なる立場や考えを持つ者同士が、誠実に向き合ったうえで成り立つものです。
つまり、真の調和は、対話を経なければ生まれない。
そしてその対話には、勇気と時間が必要です。
対話の場とは、相手を説得する場所ではなく、互いの前提を確かめ合う場。
「なぜそう考えるのか」を丁寧に掘り下げる過程で、はじめて理解と信頼が芽生えます。
“調和”よりも“対話”を重んじる組織は、意見の違いを恐れません。
むしろ、それを次の一歩に変える土壌を持っています。

■ 「衝突」を「創発」に変える三つの条件
では、どうすれば意見の衝突を組織の成長につなげられるのでしょうか。
ここでは三つの視点を挙げたいと思います。
- “目的”を見失わないこと
議論の最中に、つい「誰が正しいか」「どちらが勝つか」という方向に流れがちです。
しかし、組織における議論の本質は「何のために、それを決めるのか」という“目的”の共有にあります。
目的が明確であれば、多少の対立も“建設的な摩擦”として機能します。 - 「違い」を脅威ではなく資源とみなすこと
人は自分と異なる意見に出会うと、不安を感じます。
しかし、その違いこそが、組織の柔軟性と創造性の源です。
異なる視点を持つ人を排除するのではなく、「新しい可能性を見せてくれる存在」として受け止める意識が重要です。 - “聴く姿勢”を持つこと
対立が壊れるのは、主張がぶつかるからではなく、“聴く耳”が閉ざされるからです。
相手を理解しようとする態度がある限り、意見の違いは決して破壊的にはなりません。
「聴くこと」は、沈黙ではなく、積極的な対話の一部なのです。
これら三つの条件が整ったとき、衝突はやがて“創発”へと変わります。
創発とは、個々の意見の単なる足し算ではなく、対話の中から生まれる“予期せぬ新しい価値”のこと。
それは、誰かの主張を押し勝たせて得られる結論ではなく、関わる全員が「これなら進める」と感じる合意のかたちです。

■ 対立を恐れないリーダーシップ
健全な対立を組織の力に変えるには、リーダーの姿勢が大きく関わります。
多くのリーダーは、対立を「組織が乱れるサイン」と捉えがちですが、実際には「組織が意見を出せる健全な状態」であることを示しています。
リーダーの役割は、意見の衝突を抑え込むことではなく、対立が対話に転化する“場”を整えることです。
そのためには、意見を出した人を評価し、異論を歓迎する文化を育てることが大切です。
たとえ意見が採用されなくても、「意見を言っても大丈夫」と思える安心感があれば、組織は活性化します。
リーダーに求められるのは、「決める力」だけでなく「聴く力」。
そして、対立が起きたときこそリーダーが最も成長できる瞬間でもあります。
葛藤を避けずに引き受けるリーダーの姿勢が、組織の成熟を導きます。

■ 組織が“生きている”と感じられる瞬間
意見がぶつかるとき、私たちは疲れを感じます。
面倒だ、できれば避けたい。
そう思うのは自然なことです。
けれど、同じくらい“活気”も感じるはずです。
誰かが本気で語り、別の誰かがそれを受け止める。
その瞬間、組織は“生きている”。
そこには血の通った人間の息づかいがあります。
もし組織が、波風の立たない静かな湖のように見えるなら、それは死んでいるかもしれません。
本当の意味での成長は、痛みを伴いながらも、意見のぶつかり合いを通して起こるのです。

■ そして ― “対立”を“共創”へ
意見の衝突を恐れない組織は、変化に強い。
なぜなら、異なる声を排除しないからです。
それは単に多様性を認めるという話ではなく、異なる意見を通して自分たちの理念を更新し続ける“動的な組織”であり続けることです。
対立とは、破壊ではなく「問いの再生」です。
そして、対話を通じて生まれる共創のエネルギーこそが、組織を内側から成長させます。

“和”を保つことよりも、“わかり合う努力”を惜しまない。
その積み重ねが、組織をより強く、より人間的にしていくのだと思います。
意見がぶつかることを恐れずに、対話を選ぶ。
それが、理念を“生きた形”として次の世代へつなぐ、最も確かな道なのではないでしょうか。この事は様々な"組織"に当てはまるのだと思います。

