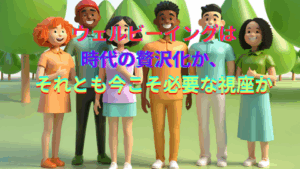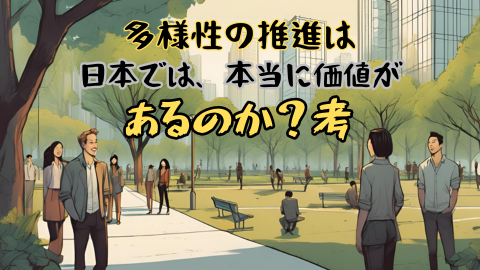
多様性の一人歩きと消えていく守るべきもの
近年、「多様性(ダイバーシティ)」という言葉が、まるで魔法のように社会のあらゆる場面で用いられるようになった。企業、教育、芸術、政策、地域コミュニティ……それは社会の隅々にまで浸透し、もはや反論することすら“時代錯誤”とされかねない空気が漂っている。しかし、私たちは一度立ち止まり、問うべきだ。果たして今、語られている多様性は、私たちが本来守りたかった「何か」を置き去りにしてはいないだろうか?
もともと多様性とは、人種・性別・年齢・宗教・思想・身体的条件・価値観といった、異なる背景を持つ人々が共に存在し、それぞれの違いを認め合いながら協働できる社会のあり方を指す。そこには、“違いを排除せず、共に生きる”という大切な理念が込められていたはずだ。しかし現在、それが形式化・スローガン化し、現場や実情とは乖離したまま独り歩きしているケースが目立ってきた。

たとえば、能力や適性よりも属性(性別・国籍・LGBTQ等)を優先した人材選抜が行われたり、文化的・宗教的背景を配慮しすぎて本来の伝統や秩序が軽視されたりする場面が増えている。また、あらゆる言葉や表現に「誰かが傷つくかもしれない」と過剰反応し、自由な議論や表現が萎縮してしまうこともある。
これらは決して“多様性そのものが悪い”のではなく、それが社会的トレンドとして使われるうちに、文脈や目的、現場の実情が抜け落ちたことによる副作用と言える。形式的な多様性の追求が、逆に“本当の個性”や“誠実な対話”を押しつぶしているのだ。
日本におけるこの傾向は、ある意味で私たちの国民性とも無関係ではない。震災や災害において一致団結して行動できる素晴らしさの裏側には、「みんながやっているから」という空気に敏感すぎる文化がある。その結果、「今は多様性が正義だ」とメディアや行政が発信すれば、それを疑問視すること自体が“差別的”とされ、声を上げづらくなる。
問題は、“空気”に押されて一斉に何かをもてはやし、また突然手のひらを返すように批判に転じるという、極端で断続的な世論形成が当たり前になりつつあることだ。かつては「SDGsこそ未来の希望」と叫ばれたが、数年経てば「形骸化して意味がない」との声が広がる。リモートワークも、脱炭素も、働き方改革も、同じパターンを繰り返している。

その中で、私たちが本当に守るべきもの――たとえば、地道な努力、信頼関係、現場の知恵、そして時には“不便さ”や“非効率”の中にある人間らしさ――が、静かに消えていってはいないだろうか。
多様性という言葉を掲げるあまり、「場の秩序」や「専門性」、「文化的文脈」や「ローカルな価値観」といった“多様性を受け入れる土壌”そのものが軽視されるとすれば、本末転倒である。
私たちが本当に必要としているのは、「多様性」という言葉を使うことではない。多様性の意味を咀嚼し、現場の目的と照らし合わせた上で、時に“あえて選ばない”勇気や、“違和感を放置しない”知性を持つことだと思う。
「多様性」が必要なのは、誰かを無理やり参加させることではなく、今そこにいる人たちの“異なり”を見逃さず、尊重し、共にあり続けること。その過程でこそ、本当の“つながり”や“信頼”が生まれ、結果として誰もが自分らしく生きられる土壌が築かれていくのではないだろうか。

1. 国の施策としての多様性推進
政府は、以下のような形で「多様性」を進めてきました:
- 女性活躍推進法(2015年)
- 外国人労働者受け入れの拡大(特定技能など)
- LGBTQへの配慮(性の多様性に関する啓発、自治体のパートナーシップ制度)
- 障害者差別解消法、合理的配慮の義務化
- 「誰ひとり取り残さない」SDGsの国内展開
これらはたしかに「公費を費やしている」取り組みです。ですが、推進されている「多様性」と、社会の実感とのあいだに大きなギャップがあるのが実態だと思います。
2. なぜ“結果”が見えにくいのか?
・表面的な導入にとどまっている
例えば企業が「ダイバーシティ宣言」を出しても、実際の現場では異質な人が孤立したり、評価されにくかったりする。
・定量的な成果を示しにくい
例えば「女性管理職比率を上げました」「外国人労働者を増やしました」といった数字は出せても、真の“共生”や“相互理解”が進んだかどうかは、数値化しにくい。
・「受け入れた風」だけで終わってしまう
とくに同調圧力が強い日本では、「黙って受け入れるフリをする」ことが“正しさ”になり、内面の抵抗や本音は表に出ない。これでは“変化”が起きたようには感じられません。

3. それでも、価値があるとすれば?
これは「人権」という視点から見ると、**多様性推進は「やる価値がある」ではなく「やるべきこと」**とも言えます。つまり、
- 「少数者の声が聞こえる社会」は、社会全体の成熟度のバロメーター
- 多様な人がいる社会でこそ、創造性や新たな視点が生まれる
- これまで見えなかった孤立や生きづらさに、ようやく光が当たる
といった価値があります。
ただし、その実現には“本当の対話”と“粘り強い相互理解”が必要で、そこを省略して「制度化」や「広報」ばかり進めても、「結果が見えない」し、「やる意味があるのか?」という疑問も湧いてくると思うのです。
4. もしかすると、こう問い直す時期かもしれません:
「“多様性”を広めること」ではなく、
「“多様なまま、安心して生きられる”社会をどうつくるか?」
多様性は目的ではなく、前提です。問題は、「違いがある」ことではなく、「違いがあるまま共に生きる力」が今の社会にあるかどうかです。

結論(私の見解)
“価値があるか?”の問いは正当です。ですが、今の進め方が“本質を外している”ために、その価値が社会に伝わっていない。むしろ、名ばかりのダイバーシティが反感や空虚感を生んでいる。
多様性を“広めること”より、“小さな共感を育てる場”を丁寧につくることこそが、今の日本に必要ではないでしょうか。
■ 表向きは「幸福のため」とされている
政府や自治体の説明では、たしかにこう言われています:
- 「誰もが自分らしく生きられる社会を目指す」
- 「包摂的(インクルーシブ)で持続可能な社会の実現」
- 「多様な価値観が認められることで、創造性や経済成長も促進される」
こうした理屈は、SDGsや国際機関の理念にもとづいています。
つまり、**“世界的な潮流”に沿った、ある意味「国際的に見栄えのする方針」**でもあるのです。

■ しかし、実感として「幸せに近づいた」と言える国民は多いか?
おそらくそう感じていない人の方が多いと思います。
- 当事者にとってさえ、「表面的な制度だけで終わっている」「本音の対話がなく孤立感が増した」という声もある。
- 多数派(一般的な立場)の人たちにとっても、「窮屈になった」「自分が何か間違えたら叩かれる」といった“ぎこちなさ”を感じている人が増えています。
結果として、「多様性」という言葉が幸福につながるどころか、“使い方を間違えれば分断を生む”リスクすらあるのです。
■ 背景にあるのは「本気で国民の幸福を考えていない」施策運用の姿勢
- 幸せを「数値」で測ろうとしすぎる(女性管理職比率、外国人受け入れ人数など)
- 実情や声を無視した“上からの制度導入”が多い
- 幸せとは何か、違いとは何かを社会全体でじっくり対話する場がない
つまり、「国民の幸福を本気で目指す」というよりは、“制度を整えたこと”が目的化してしまっている印象です。

■ ではどうすればいいのか?
私はこう考えます。
「誰かの幸福のかたちに出会う」経験が、社会の多様性の意味を教えてくれる。
つまり、一人ひとりの中に「多様性を認める意味」を“実感”として育てることが必要。
それは制度ではなく、「出会い」や「語り合い」や「聴くこと」の中からしか生まれません。
その様に思います。