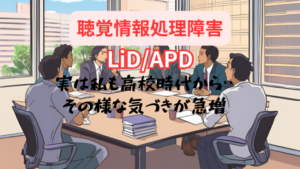3月28日配信の記事です。
和歌山市にある障害者支援施設「ビンセント療護園」で、職員7人が利用者15人に対し虐待を行ったとして、行政処分を受けました。
和歌山市によりますと、去年9月、関係者からの内部通報を受けた法人が市に報告し、その後、市が聞き取り調査などを行った結果、7人の職員が、利用者15人に対し虐待をしていたことが確認されたということです。(記事3/28ヤフーニュース)
大変複雑で、難しい問題ではありますが、思う事を書かせて頂きます。

重度精神・身体障害者施設における虐待の問題や、過去に起きた痛ましい事件を振り返るとき、そこには単なる個人の問題ではなく、社会全体の構造的な課題が横たわっていることを痛感します。私は以前、「生きるのに理由はいるの?」というドキュメンタリー映画を制作された澤則雄監督と直接お会いし、様々なお話をお聞きしたり、また映画の中においても、それはもう、とてもとても考えさせられました。その中で浮かび上がったのは、施設の在り方、入所者家族の現状、そして国の対応の問題でした。
中でも、ドキュメンタリー映画の中で感じた、私も経験のある「預けざるを得ない事情」という、どうしようもない部分との葛藤なんですね。一部分の家族は、施設の現状を多少は理解していながらも、やむを得ず大切な家族を預ける選択をしているような現実がそこにはあるのでは?現場の人手不足、職員の精神的負担、入所者への偏見、社会の関心の低さ――これらすべてが絡み合い、「施設とはそういうもの」という諦めのような認識が社会全体にも根付いてしまっているのではないでしょうか。

しかし、果たしてそれでいいのでしょうか。こうした状況を放置することは、次なる悲劇を生むことにつながります。実際、過去に起きた重大事件も、単なる個人の思想や行動の問題ではなく、社会の無関心が助長した結果であるとも考えられます。特に、施設が閉鎖的な環境になってしまうことで、入所者の人権が軽視される状況が生まれやすくなります。
この問題を解決するには、国が強力に動かなければなりません。現在の対応は、結果的には「放置状態」と言わざるを得ません。たとえば、施設の監査制度は形骸化しており、内部告発も難しい環境があります。また、介護職員の待遇改善も十分とは言えず、疲弊した職員が適切なケアを提供できなくなっている現実があります。

必要なのは、まず施設の透明性を高めることです。施設の運営が社会に開かれ、地域住民や家族が日常的に関わる仕組みをつくることで、閉鎖的な環境を改善できます。また、職員の待遇改善とメンタルヘルスサポートを強化することで、現場の負担を減らし、入所者に対するケアの質を向上させることが求められます。
さらに、社会全体の意識改革も不可欠です。障害を持つ人々を「支援が必要な存在」としてではなく、「共に生きる社会の一員」として捉える価値観を広めなければなりません。そのためには、教育やメディアを通じた啓発活動が重要となります。

私は「社会とつながる場をつくる」という活動を進めていますが、この問題も本質的には「つながりが断たれることで、施設が閉鎖的になり、問題が表面化しにくくなる」という構造が背景にあります。障害の有無にかかわらず、多様な人が関わりを持つことが、最も根本的な解決策の一つではないでしょうか。
この問題の解決は簡単ではありません。しかし、国が積極的に介入し、社会全体が「無関心」という姿勢を改めない限り、現状は変わりません。私たち一人ひとりが、この問題に目を向け、具体的な行動を起こすことが、未来の社会をより良いものにする第一歩になると思っています。