
現在の社会がどのような方向に変化しているのかを考える際、物販のPRの方向性を見ると、その傾向が分かることが多いように思います。もちろん、戦略的に特定の方向へ誘導する意図もあるかもしれませんが、大半は社会の流れに沿ったものではないでしょうか。例を挙げます。
以前から、クラフトビールを製造するヤッホーブルーイングに注目していました。彼らはクラフトビールの味わいを楽しむことに加え、人との交流を通じて生まれる幸福感を訴求していると感じます。実際、そのような考え方は文献にも記されています。たとえば、飲用者同士が語り合える「場」を設けてイベントを企画したり、「寄り添うビール」として周囲の人と笑顔で過ごせる時間を提案したりするなど、さまざまなコミュニティを生み出す取り組みを行っています。非常に興味深い戦略だと思います。これも考え方のリデザイン化と言えるでしょう。
ウェルビーイングを中心に据え、それを実現するために自社の商品を活用する——こうした考え方は、まさに時代に合った戦略ではないでしょうか。それだけ社会全体が「個人の幸せ」に目を向けるようになっていることの表れだと感じます。このこと自体、考え方のリデザイン化と言えるでしょう。

以前にも書きましたが、医療・福祉分野のリデザインに関して・・
医療・福祉分野におけるリデザイン
医療や福祉の分野でも、従来の仕組みの限界が指摘されています。特に、患者と医師の間のコミュニケーション不足、医療リソースの偏在(医師の数や診療科が地域ごとに大きく偏っていること)、超高齢社会への対応などが課題となっています。
従来の医療システムは、「治療する」ことに重点を置きすぎており、患者の生活全体を考慮したケアが不足していました。しかし、近年では「患者中心の医療」が重要視されるようになり、医療提供のあり方そのものがリデザインされています。例えば、オンライン診療の普及や、地域包括ケアシステムの導入などは、その一環といえます。
また、福祉の分野では、支援を「受ける側」と「提供する側」を明確に分ける従来のモデルから、「共に支え合う」モデルへの転換が求められています。障がい者や高齢者が地域の一員として役割を持てる仕組みを作ることも、リデザインの一例でしょう。
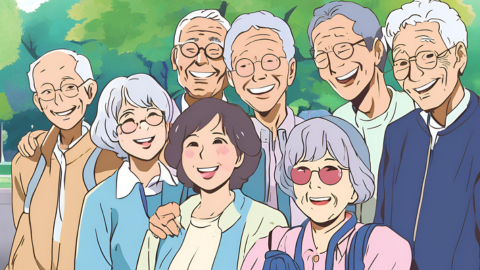
『Terminal Station for Connecting with Society』社会と繋がるターミナルステーション/リデザインの凝縮
私達の構想しているターミナルステーション、この場所は、誰もが気軽に立ち寄れる「人が寄れる場」「交わりの場」です。しかし、それだけでなく、ここに集まる人々が自然と社会貢献(利他性)について考えられる場所にしたいと考えています。「幸せになりましょう」と言葉で伝えるだけではなく、それぞれが自分なりの幸せを見つけられるきっかけやアイテムを提供し、共に考え、行動できる場を目指しています。幸せ感が高ければ健康寿命も延びます。(3/3投稿・しあわせ感が健康寿命を延ばす)
そのために、社会の流れを敏感に感じ取り、「今、この時代に必要なもの」を具体的な形で提案していきます。しかし、それを決めるのは私たちだけではありません。「どんな社会貢献ができるのか?」「私たちは何を大切にしたいのか?」—— ぜひ、皆さんと一緒に考えたいのです。
ここでの気づきや対話が、新たなつながりや行動につながる。そんなステーションを、皆さんと共に創っていきたいのです。


