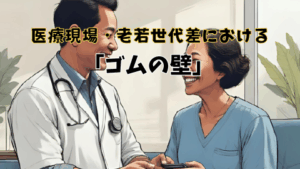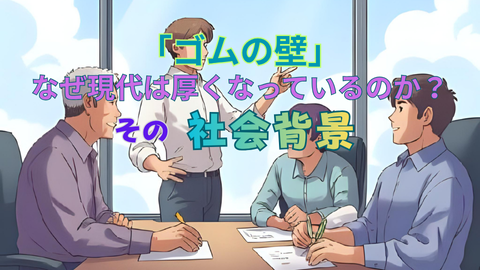
社会背景からの考察
現代社会では、多くの人が「話が届かない」「理解し合えない」「心に触れられない」という感覚を抱えながら生活している。これは単なる個人のコミュニケーション能力の問題ではなく、人間の心に生じる防衛機能、いわゆる「ゴムの壁」が以前よりも厚く、強固になっていることと深く関わっている。この現象にはいくつかの社会的背景が複雑に絡み合っており、特にコロナ禍以降の孤立化、価値観の多様化、情報環境の変化、経済的不安定性、心理的負荷の慢性化などが大きく影響している。

■ 1. コロナ禍による「心の引きこもり化」
2020年以降のコロナ禍では、物理的な距離だけでなく、心理的な距離も広がった。マスク生活によって表情が読めず、声がこもり、特にAPD(聴覚情報処理障害)のある人や高齢者などは「コミュニケーションが成立しない」「間違われる」「理解されない」という体験が積み重なった。その結果、多くの人が「どうせ伝わらない」「話すのが疲れる」という学習をし、心を守るために壁を厚くしていった。
さらに、リモートワークやオンライン授業が普及したことで、「人間関係は最小限でいい」という気分が社会全体に広まった。これは表面的なストレスが減る一方で、「深い関係」や「心の触れ合い」を避ける方向に働き、心の壁を強くする作用を持った。

■ 2. 情報過多と「心のキャパシティの限界」
現代人は、1日に触れる情報量が江戸時代の一年分に相当するといわれるほど、圧倒的な情報環境にさらされている。SNS、ニュース、動画、広告、あらゆる情報が絶え間なく流れ込み、脳は選別しきれない。
心理学では、情報過多は「認知的疲労」と「情動の鈍化」を引き起こす。つまり、感情の動きが鈍くなることで、他者の言葉が入ってこなくなる。これは“心を守るための省エネモード”のようなもので、外界の刺激を跳ね返す「ゴムの壁」が強化されてしまう。
また、SNSは常に比較を生む。誰かの成功や幸せの記録を見るたびに、「自分は不十分だ」という感情が生まれ、それを感じなくて済むように心が閉じていく。「壁」を厚くすることで、自尊心を守ろうとするのである。

■ 3. 多様性の進展が「摩擦の増加」につながっている皮肉
「多様性」「インクルージョン」という言葉は社会的に強調されているが、人々の認知は追いついていない。価値観が多様になればなるほど、「分かり合えるはず」という期待が裏切られやすく、違いを受け止めきれない場面が増える。
特に日本社会では、同質性と空気の共有が長く文化の基盤だった。そのため、本来は差異を理解するための努力が必要なのに、「何となく分かるはず」という暗黙の前提が崩れたことで混乱が生じている。
“わからない”ことへの耐性が低い社会では、人は心を守るために壁を作る。違いに触れるたびに疲れ、誤解されるたびに傷つく。多様性が広がるほど、paradoxically(逆説的に)、個人の「ゴムの壁」は強固になる。

■ 4. 経済的不安と将来の不透明さ
現代の若者は、「努力すれば報われる」という成功方程式が崩れた世界を生きている。終身雇用は崩壊し、年金も不確か、物価は上がり、共働きが前提。中年・高齢者も同様に、キャリアの見通しがなくなり、老後の不安が増す。
経済的不安は、人間を防衛的にする。心理学でも、将来の不安は「他者への信頼の低下」「感情共有能力の低下」と強く関わることが示されている。心に余裕がなくなると、他者の言葉が入ってこない。「ゴムの壁」が厚くなるのは自然な反応といえる。

■ 5. 世代単位での「孤立化」の進行
現代の個人主義は、自由をもたらす一方で「つながりの希薄化」を生んだ。家族、地域、職場のつながりは弱くなり、相談できる人が極端に減っている。孤立は心の壁を厚くする。人は孤独のなかで、一層自分を守ろうとするからだ。
特に日本では、“迷惑をかけない”ことが美徳とされるため、人は悩みを内側に抱え込み、結果として心の壁が強化されてしまう。

■ まとめ:現代は「傷つきやすさ」と「防衛の強さ」が共存する時代
現代人の心は、表面的には柔らかく見える。しかし内側には、非常に頑強な防衛壁が存在する。情報過多・経済的不安・価値観の多様化・孤立という複合的な環境の中で、人々は「これ以上傷つかないように」と無意識にゴムの壁を厚くせざるを得ない。

これは弱さではない。現代社会の複雑さに対する、生存のための適応である。しかし、この壁が強固すぎると、つながりが断たれ、幸福感が低下し、社会的分断が深まる。まずは各々がこの状況を理解することが必要かと思う。