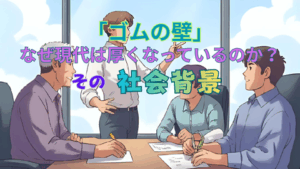一見やわらかく、押せばへこむのに、決して壊れず、元に戻ってしまう壁
このイメージから生まれた心理的メタファーです。お聞きになったこと、ありますか?
■ ① 他者とのコミュニケーションでの「ゴムの壁」
相手がこちらの言葉をいったん受け止めるように見えるのに、本質的にはまったく響いておらず、いくら話しても中に入っていかない状態を指します。

例
- 「そうですね、わかります」と言うのに、結局まったく行動が変わらない
- こちらの気持ちを返してはくれるが、本質的な“つながり”が感じられない
- 話が“吸収されず”“跳ね返される”ような感覚
この場合の「ゴムの壁」は、防衛的な心理、自己保全、感情を感じたくない回避などが背景にあることが多いようです。

■ ② 自己の内面にある「ゴムの壁」
自分の中に潜んでいる、
変わりたいのに変われない・気持ちを直視できないときの内部抵抗を指す場合もあります。
よくある背景
- トラウマや傷つき体験を守る“こころのクッション”
- 親密さへの恐れ
- 批判・失敗への防衛
- 自己像が崩れることへの無意識の回避
この「ゴムの壁」があると、外からのフィードバックやアドバイスが入ってこない、自分の感情も扱えない、そんな心理的停滞が生まれます。

■ ③ どのように接すれば?
**「言葉ではわかっているけど、心には届かない」**ときに「ゴムの壁がある状態」と表現されることがあります。
これは病気ではなく、誰にでも起こりうる普通の心理的防衛メカニズムです。
🧩 なぜ「ゴム」なのか?
- 硬くはない: 一見柔らかく対応できる
- 壊れない: 根本に触れる前に弾き返す
- すぐ元に戻る: 変化(学習・気づき)が持続しない
という特徴を示すための比喩です。

🌱 「ゴムの壁」があるときのヒント
- 急がない
壁は急に破れるものではなく、時間が必要です。 - 安全な関係づくりが最優先
壁は“危険”を感じると厚くなります。 - 感情への直接的アプローチを避ける
いきなり核心に触れるより、周辺を丁寧に扱うことで薄くなります。 - 体験ベースの関わり
「気づき」より「経験」が壁を弱めます。
このような考え方での対応が良いと聞きます。
様々なシーンにおいて、たとえば①「医師と話すときのポイント」や、②社会のつながりをつくる活動にも、実はこの“ゴムの壁”の存在は非常に重要な概念だと思います。人は皆、心にそれぞれのゴムの壁を持っており、その厚みがコミュニケーションの難しさを生みます。
明日以降、①と②について考えていきたいと思います。