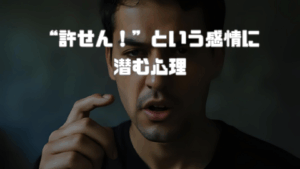静寂のなかのノイズ社会で・・・
「音は聞こえるのに、言葉がわからない」。
この訴えをする人が、ここ数年で確実に増えているといわれます。聴覚情報処理障害(Auditory Processing Disorder:APD)は、耳そのものの聴力には問題がないのに、聞いた音声を脳でうまく処理できない状態を指します。大阪公立大学附属病院をはじめ、専門外来の予約が数か月待ちになるほど受診希望者が殺到しているというのも、決して誇張ではありません。潜在的な患者数は240万人ともいわれ、かつて「聞こえにくさ」は高齢化の象徴とされていた時代から、今や若年層を含む広い世代の課題へと変わりつつあります。では、なぜいまAPDが増えているのでしょうか。

1.音の洪水の中で「選び取る力」が疲弊している
私たちは日常的に、膨大な量の音にさらされています。電車のアナウンス、カフェのBGM、スマートフォンの通知音、職場の雑談――どれも「情報」としての音です。
かつて人間の聴覚は、自然界の音に反応し、危険や仲間の声を察知するために発達しました。しかし現代社会では、音の大半が“人工的ノイズ”です。聴覚は常に過剰な刺激にさらされ、脳は重要な音とそうでない音を仕分け続けています。
この「選び取る力」こそが、聴覚情報処理の中枢的な働きです。注意・記憶・言語理解と密接に連動しており、集中力やストレスの影響を強く受けます。情報過多社会のなかで、脳は常にフル稼働状態にあり、認知的疲労(cognitive fatigue)は日常化しています。APDの増加は、単なる感覚器の問題ではなく、「情報処理に疲れた脳の悲鳴」とも言えるでしょう。
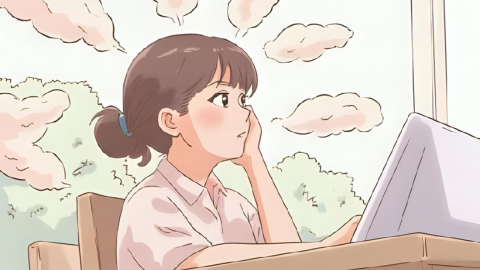
2.マスク社会とコミュニケーション不全
コロナ禍以降、APDの訴えが一気に増えた背景には、「マスク社会」があります。
口の動きや表情、息づかいは、言葉を理解するうえでの重要な視覚情報です。私たちは無意識のうちに、耳と目の両方を使って他者の話を理解しています。ところがマスクによってその手がかりが遮断されると、聴覚だけに負荷が集中します。
さらに、医療機関や公共施設などの受付では、アクリル板越しにマスクで話すという「二重の遮断」が起こり、言葉の聴取が格段に難しくなりました。特に高齢者や疲労のある人、脳の処理機能が低下している人にとって、これが大きな負担となっています。結果として、「相手の声がこもって聞こえる」「言葉が入ってこない」「会話が怖い」といった二次的な心理的苦痛を引き起こすのです。

3.脳の“認知資源”の枯渇とストレス社会
APDの背景には、神経心理学的な側面もあります。
脳は、聴覚皮質で音を分析し、その情報を前頭葉や側頭葉で統合・理解します。ところが、慢性的なストレスや睡眠不足、うつ症状、過労などが続くと、脳の「認知資源」が枯渇します。これは、パソコンでいうメモリ不足のような状態です。
情報処理の一部が滞ると、音声理解のプロセスにも遅延が生じます。音は聞こえるのに意味が取れない――そのギャップがAPDの特徴的な苦しみです。また、疲労による前頭葉機能の低下が、注意の切り替えを難しくし、雑音環境での聴取をさらに困難にします。
この点で、多発性硬化症(MS)などの神経疾患とAPDには共通する要素があると感じております。どちらも「脳の情報処理能力」が疲弊している状態であり、身体的な疲労だけでなく、思考や感覚レベルでの“処理疲労”が関与しているのです。

4.「孤立」と「過剰なつながり」のはざまで
APDの増加を語るとき、見逃せないのは現代人の「コミュニケーション疲れ」です。
SNSを通じて常に誰かとつながっているように見えても、実際の対話は浅く、相手の表情や声色から情報を得る機会は減りました。リアルな会話が減少すれば、聴覚による「他者理解の訓練」も失われます。人の声に耳を傾ける時間が減り、結果として聴覚的注意や音声の識別能力が衰えていく――これは、社会的スキルの変化と神経的変化が連動している例と言えるかもしれません。
一方で、オンライン会議や音声メディアなど、耳だけで情報を受け取る場面は急増しています。多すぎる声、多すぎる情報、多すぎる反応。APDは、まさに「孤立と過剰なつながり」のはざまで生まれた時代の症候なのかもしれません。

5.「見えない障害」としての理解不足
APDが厄介なのは、外見からはまったくわからないことです。聴力検査では異常なし、MRIでも構造的な異常は見つからない。それゆえに、「気のせい」「集中力がないだけ」と誤解されやすいのです。
しかし、APDは明らかに“脳の機能障害”としての側面を持ちます。情報処理の過程に問題があるため、本人の努力や根性では克服できません。にもかかわらず、周囲の理解が乏しいまま、本人が自己否定に陥るケースも少なくありません。
学校や職場では、聞き返しを繰り返すことへの罪悪感や、会議中に内容が追えない焦りが積み重なり、結果的に社会的な孤立を深めていきます。この「二次的な心理的負担」が、APDの真の苦しみだと私は思います。

6.増加の本質は「社会の聴覚過負荷」
では、なぜいまAPDが増えているのか。
私はその根底に、「社会全体の聴覚過負荷」があると考えています。
それは単なる物理的な騒音だけでなく、心のノイズ、情報のノイズ、人間関係のノイズをも含みます。
私たちは常に何かを聞き、反応し、判断し続けています。休む暇のない聴覚と脳は、やがて処理の優先順位をつけられなくなり、重要な音を“見落とす”ようになる。これは現代社会そのものの疲れの象徴でもあります。
APDの増加は、「個人の病」ではなく、「社会の症状」として捉える必要があります。
働き方の多様化、デジタル化、そしてコロナ禍後の不安定なコミュニケーション環境――それらが複合的に作用し、聴覚処理という繊細な仕組みに影響を与えているのです。

7.“静けさ”を取り戻すというケア
APDに対して今すぐできる特効薬はありません。けれども、環境を整えることはできます。静かな空間で話す、相手の顔を見て話す、短い文でゆっくり話す――そんな小さな配慮が、大きな救いになります。
そして何より、「疲れた脳を休ませること」。
自然の音を聴く時間を持つ、デジタルデトックスを行う、音楽や読書に没頭する。これらは単なるリラクゼーションではなく、聴覚処理能力のリセットにもつながります。
私たちは、「聞こえない人を理解する社会」だけでなく、「聞こえすぎて疲れている人を癒す社会」を作らなければならない段階に来ているのかもしれません。

― “耳の不調”は“心のサイン”でもある
聴覚情報処理障害の増加は、私たちがいかに疲れ、焦り、そして情報に押しつぶされているかを映す鏡のようなものです。
APDの本質は、「音を聞く」ことよりも、「他者の声を受け取る」ことにあります。声が届かないのは、耳ではなく、心のキャパシティが限界に達しているからかもしれません。
誰もが安心して「もう一度、ゆっくり話してください」と言える社会。
それが、APDという静かな病に対して、最も優しい治療の第一歩だと思います。