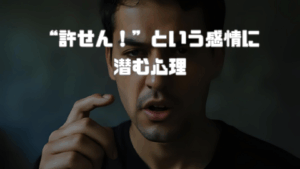多発性硬化症と「思考疲労」の本質
病気確定27年の当事者であります投稿者の実体験、そして大阪公立大学大学院医学研究科 脳神経内科学 武田 景敏先生の当団体での過去のご講演や、その他参考文献より私なりに解釈したところを書いてみます。多発性硬化症を含む中枢神経系の難病には共通するテーマと思います。
多発性硬化症(MS)は、免疫系の異常により中枢神経の髄鞘が損傷を受けることで知られています。その結果、神経伝達が阻害され、運動障害や視覚障害、感覚異常など多様な症状を引き起こします。ところが、この病気において最も日常生活を左右する症状のひとつが、「疲れ」なんです。
この疲れは、単なる「疲労感」ではありません。休んでも取れず、体力というより“脳の処理能力”そのものが低下しているかのような状態です。当事者の方々がしばしば口にされるのは、「頭を使うことが、肉体労働よりも消耗する」「考えることそのものが重い」という感覚です。これは、いわば“思考の疲労”とも言えるものです。

■ 脳のネットワーク疲労 ― 目に見えない「信号の渋滞」
MSの病理の特徴は「脱髄」です。神経を覆う絶縁体である髄鞘が失われることで、神経信号の伝達速度が低下します。この現象は、電線の被膜が剝がれた状態を想像するとわかりやすいでしょう。信号の漏れや遅延が生じるため、脳は本来よりも多くのエネルギーを使って情報処理を行わざるをえません。
近年のfMRI(機能的MRI)による研究では、MS患者が認知課題を行う際、健常者よりも広い脳領域を動員していることが確認されています。
つまり、脳は「補償的」に働いているのです。壊れた配線を迂回しながら、なんとか目的地に信号を届けようとする。結果として、思考や判断、注意の維持に必要な神経活動が過剰になり、**“思考そのものが疲れの原因になる”**のです。
この「代償的過活動」は短時間なら機能しますが、長期的には脳のエネルギー消費を増大させ、神経細胞に負荷を与えます。その結果、集中力の低下、感情の不安定化、動機づけの減退といった症状につながることもあります。実体験しております。

■ 「考えることがつらい」という新しい現実
MSの疲れは、体を動かさなくても生じます。むしろ、静かな環境で考えごとをしている時こそ、深い疲れに襲われるという声は少なくありません。
「誰かと会話した後、何時間もぐったりして動けない」
「頭で理解しようとするだけで、脳のどこかが軋むような感覚になる」
これは決して“気のせい”ではなく、病理学的にも説明がつく現象という事です。
神経科学的に見ると、MS患者の脳では“グルコース代謝”の効率が低下していることが知られています。つまり、脳のエネルギー源である糖をうまく利用できず、思考を維持するための燃料が不足している状態です。
このため、会話・判断・記憶といった「認知的活動」が、健常者に比べてはるかに高いエネルギーコストを伴うのです。
この状態を経験する人の多くは、「怠けているように見られる」ことに苦しみます。外見は健康そうに見える一方で、内側では思考のプロセスそのものが摩耗している。この**“見えない疲労”**こそ、MSの大きな社会的課題でもあります。

■ 「脳のスタミナ」という概念
一般的に、私たちは疲れを筋肉や体力の問題と捉えがちです。しかしMSにおいては、「脳のスタミナ」という概念がより重要になります。
脳はエネルギーの消費が非常に激しい臓器であり、全身のエネルギーの約20%を使うといわれています。健常な脳では、効率的な神経伝達により、必要な時に必要なだけエネルギーを配分できます。
しかし、脱髄や軸索損傷によって神経経路が不安定になると、脳全体が無理をして働くようになり、スタミナが急速に尽きるのです。
この“脳のスタミナ切れ”は、ある瞬間に突然訪れることがあります。
「午前中は普通に話せたのに、午後には何を言われても頭に入ってこない」
「文章を読んでも意味がつながらない」
これらは、情報処理のための神経回路が“燃料切れ”を起こしている状態です。

■ 感情と疲れ ― 思考と情動は同じエネルギーを使う
MSの疲れを考えるとき、見逃せないのが「感情」の関与です。感情のコントロールや共感、ストレス耐性といった情動の処理も、前頭葉や辺縁系など脳の高次機能を使います。
つまり、感情の動きもまた“エネルギー”を消費します。
そのため、たとえば「人の話を聞く」「共感を示す」といった行為も、MSの当事者にとっては大きな負担になり得ます。人との関わりは大切である一方で、その関係性の維持にも膨大な脳的エネルギーを要するのです。
この点は、外見からは理解されにくく、誤解を生みやすい部分でもあります。

■ 「疲れ」とともに生きる ― 思考のリズムを取り戻す
では、どうすればこの“脳の疲れ”と付き合っていけるのでしょうか。
第一に大切なのは、「疲れを症状として正当に認識する」ことです。MSの疲労は怠けでも甘えでもなく、明確な病理的現象です。その理解を周囲が持つことが、社会的サポートの第一歩になります。
第二に、**「思考のリズムを整える」**ことです。MSの脳は、フルスピードで動かし続けると容易にエネルギー切れを起こします。
ですから、「考える時間」と「何も考えない時間」を明確に分けることが重要です。短時間の集中と休息を繰り返す、いわば“脳のインターバルトレーニング”です。
思考や感情の動きを一時停止させるマインドフルネス的な方法も有効です。
第三に、社会的理解の醸成です。
「見えない疲れ」に対する無理解が、当事者の孤立を生みます。もし社会全体が、「脳が疲れる」という概念を共有できれば、職場や家庭での対応も変わるはずです。
MSの疲労は、“個人の体調”の問題ではなく、“社会の理解”の問題でもあるのです。

■ むすび
多発性硬化症における「疲れ」は、単なる倦怠ではなく、脳そのものが疲弊する現象です。
思考する、感じる、判断する――人間らしい営みのすべてが、エネルギーを必要とします。
そのエネルギーが枯渇する苦しみは、外から見えないからこそ深いのです。
しかし、そこにこそ、人間の尊厳の一面があります。
限られたエネルギーの中で、今日も考えようとする。言葉を紡ごうとする。
それは、脳が損なわれても、心が決して損なわれないことの証でもあります。
脳の病理は人の可能性を奪うものではなく、**“生きる力の配分を変える”**ものなのかもしれません。
思考に疲れを感じるその瞬間こそ、脳が懸命に働いている証。
そして、その事実を社会が理解することが、MSの本当の支援のはじまりだと思うのです。

付録
📋 実務・支援活動への例
今後必要になると考える様々な対策
- 疲労の出現や悪化を“見逃さない”ためにも、支援対象の方(MS含め多くの難病患者)に対して 疲労スクリーニング(例:簡易疲労尺度) を定期的に行う仕組みをつくる。
- 疲れを「ただの休息不足」と捉えず、「中枢神経の変化+身体・心理・生活習慣の複合影響」という視点を持つように支援者を指導・啓発する。
- 支援プログラム設計時に「運動・身体活動」「睡眠・休息習慣」「精神的ケア(うつ・不安)」「生活リズム・クーリング(暑さ/気温影響も報告されています)Frontiers+1」を統合的に入れる。(Frntiers+1→他サイト参照、英文・・翻訳してください。)
- 測定手法・評価指標を明確にし、支援前後で「疲労の変化」を可視化できるようにすることで、プログラムの効果検証や参加者の実感促進につなげる。
- 支援対象がMS以外の難病・障害を抱えていても“疲労”という共通課題として、「MSの疲労研究」の知見を横展開可能。