
教育と社会が育てた“孤立の構造”
私たちはいま、かつてないほど「人とつながる手段」に恵まれた時代を生きています。SNSを開けば、世界中の人と瞬時に連絡が取れる。オンライン会議で遠隔地の仲間と仕事を進められる。けれど、皮肉なことに、これほど便利になった社会で「孤独」を訴える人が増えています。とりわけ中高年層の間で、家族以外との関係が希薄になり、社会との接点を失ってしまう人が少なくありません。
なぜ、これほど“つながりやすい”社会で、“つながれない人”が増えているのでしょうか。その背景には、幼少期からの教育や家庭環境の変化、そして社会構造そのものの変質が深く関わっているように思います。

■ 「他人と比べない教育」の光と影
1980年代以降、日本の教育現場では「個性を尊重する」「他人と比べない」教育が推進されてきました。偏差値や順位で序列をつけるのではなく、一人ひとりの良さを認めようという考え方は、確かに時代の要請でもありました。行き過ぎた競争が子どもを苦しめてきた反省から生まれた流れでもあります。
しかし、その“やさしい教育”は、同時に「他者とどう関わるか」を学ぶ機会を減らしてしまった面もあります。たとえば、意見がぶつかったときにどうすればよいのか、相手の気持ちを推し量りながら妥協点を見出すにはどうしたらいいのか――そうした「社会的な摩擦」を経験する場が少なくなりました。
子どもたちは「自分を大切にしよう」と教えられますが、「他人を尊重するとはどういうことか」という“実地の体験”が伴わないまま大人になっていくケースが増えています。
結果として、相手と意見が食い違うことへの“耐性”が弱まり、少しでも衝突しそうになると「関わらない」「距離を取る」方向に逃げてしまう。こうした傾向は、のちに人間関係を築くうえでの大きなハードルとなります。
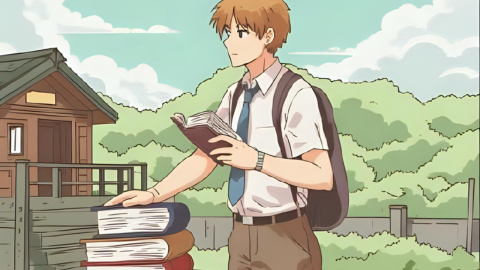
■ 家庭の中で失われた「小さな社会」
もう一つの変化は、家庭そのもののあり方です。かつての家庭には、祖父母・両親・子どもが同居する“多世代家族”が多く存在していました。そこでは、世代間の価値観の違いや、生活習慣のずれが日常的に起きていました。
「おじいちゃんの言うことは古い」と思いながらも、我慢して聞いたり、反論して怒られたり。そうしたやりとりの中で、自然と“他者と生きる力”が養われていたのです。
しかし、核家族化が進み、家庭の中から多様な価値観の“摩擦”が消えました。加えて、共働き世帯の増加により、親が子どもと過ごす時間が減少し、親子の会話そのものが少なくなっています。
家庭が“教育の場”としての機能を果たしきれなくなり、「社会性の種」をまく場がどんどん縮小しているのです。
その結果、「他者と違っていても共に過ごす」「嫌なことを言われても立ち直る」といった“感情の免疫力”が育ちにくくなっています。この小さな免疫の欠如が、やがて社会に出たときに「人づきあいが苦手」「誰かと一緒にいると疲れる」という感覚となって表れます。

■ SNSが作り出した“疑似つながり”の世界
そして現代において、人間関係のあり方を最も変えたのがSNSの登場です。
一見、SNSは人と人を結びつける強力なツールのように見えます。しかしその“つながり”は、実際には非常に脆く、表層的なものであることが多いのです。
SNS上では、相手の“都合の良い一面”しか見えません。投稿は加工され、感情は演出されます。そこには「本音でぶつかる」場面がほとんど存在しません。衝突や誤解が生じそうな会話は避けられ、同調圧力の中で“心地よい共感”だけが残る――それがSNSの特徴です。
つまり、リアルな人間関係に欠かせない「摩擦」「葛藤」「回復」のサイクルが、そこにはないのです。
また、SNSでは常に他人の成功や楽しそうな姿が目に入ります。すると、自分との比較が止まらず、「自分だけが取り残されている」と感じてしまう。
本来、“比べない教育”で育ったはずの世代が、皮肉にもSNSで最も強く“比較”に苦しむようになっています。

■ 「衝突を避ける社会」が生むミドルの孤立
こうして、子どもの頃から「衝突を避ける」「自分を守る」ことを学んできた世代が、大人になって社会の中枢に立つようになりました。
職場では、波風を立てないように振る舞い、家庭では本音を抑えて“うまくやる”。一見、協調的に見える生き方ですが、その実態は「本当の意味で他者と向き合えていない」状態とも言えます。
特に中年期に差しかかると、仕事や家庭での役割の変化、親の介護など、人生の負荷が増していきます。そのときに、頼れる人間関係がないと、心は一気に孤立してしまうのです。
「誰にも弱音を吐けない」「本音を言える場がない」という人が増えているのは、こうした社会構造の結果でもあります。
かつての日本社会には、“ご近所づきあい”や“飲みニケーション”といった、非公式なつながりの場が存在しました。それらは面倒でもありながら、人間関係の潤滑油として機能していました。
しかし、効率と合理性を重んじる現代では、そうした“無駄な関係”が排除されてしまいました。結果として、表面上は平穏でも、内側では誰もが孤立しやすい社会構造ができあがっているのです。
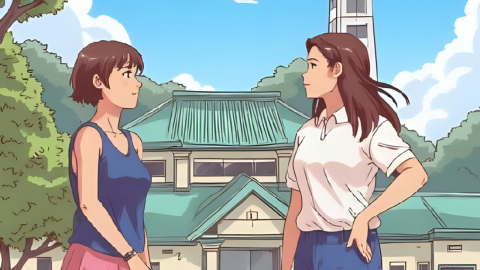
■ つながる力を「再教育」する時代へ
では、私たちはどうすれば「つながり下手」から抜け出せるのでしょうか。
それは、“他者との摩擦”を恐れないことから始まると思います。人と意見が違っても、価値観が合わなくても、「それでも一緒にいる」こと。その経験こそが、人間関係の耐性を育てます。
また、教育の場でも「協働」や「対話」を中心とした学びを再構築する必要があります。子ども同士が意見を出し合い、時にぶつかりながら答えを探す。そうした経験は、単なる知識よりもはるかに深い“社会的な学び”です。
そして、大人もまた“学び直し”が必要です。
ミドルエイジこそが、もう一度「つながる練習」を始める時期だと思います。

地域の活動やボランティア、趣味のコミュニティなど、利害を超えた関係の中に身を置くこと。そこでは、相手を尊重しながら自分を表現する力が自然と磨かれます。
「人と関わるのは疲れる」と感じるのは、自分を守りすぎてきた証でもあります。心の鎧を少しだけゆるめ、互いに“弱さを見せ合う”ことから、真のつながりは始まります。
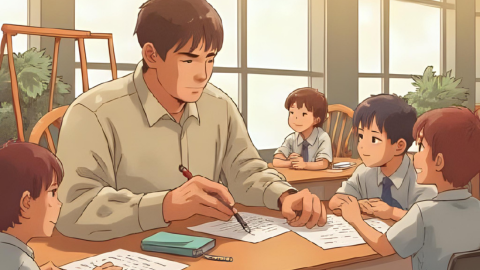
■ 終わりに ― 孤立の時代を超えて
“つながり下手”とは、決して個人の性格や能力の問題ではありません。それは、教育や社会の仕組みの中で徐々に育ってしまった“構造的な孤立”なのです。
しかし、その構造をつくったのが社会であるならば、壊すこともまた、社会にできるはずです。

私たちはいま、改めて「人とどう関わるか」という問いを突きつけられています。
SNSでの“つながり”を超えて、顔の見える関係へ。
個性を重んじながらも、他者と生きる知恵を取り戻すこと。
その一歩を踏み出す勇気こそが、孤立の時代を越える希望になるのではないでしょうか。

