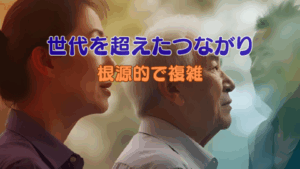― 「空気のような存在」としての愛を問い直す ―
1.「当たり前」の中で忘れ去られるもの
私たちは日々の生活の中で、数えきれないほど多くのものに囲まれて生きています。食事、住まい、インフラ、健康、そして人間関係。その一つひとつが揃っているからこそ、私たちは安心して眠り、翌朝を迎えることができます。ところが、その大切なものの多くは、いざ不足したときに初めて「自分にとって不可欠だったのだ」と気づくのです。
愛もまた、その典型といえるでしょう。話は変わりますが、昔、NHKのテレビで『マンガ教室』とい番組があり、小学生だった私は毎週観ていました。内容はこれまで記憶があいまいでしたが、この半年間朝ドラで『あんぱん』が放送された事により呼び戻されると同時に、番組の先生だった「やなせ たかし」氏の人間性や作家魂が少し理解できるようになり、今回このようなテーマにも繋がっています。

話を戻しまして、家族、友人、恋人、あるいは社会から受け取るさまざまな愛情や思いやり。それらは、生きる上で根幹を支える力であるにもかかわらず、しばしば「あるのが当たり前」と思われ、意識の外へ追いやられます。
ではなぜ、愛は「当たり前」になると見えなくなってしまうのでしょうか。そして、それを見失うことは、人間の心にどのような歪みをもたらすのでしょうか。
2.「愛」を認識する難しさ
まず考えたいのは、愛という概念自体の「つかみにくさ」です。愛は明確な形や数値で表せるものではなく、感覚的・情緒的な体験として存在します。たとえば、誰かがこちらに微笑みかける、料理を作って待っていてくれる、体調を気遣う一言をかけてくれる。これらの行為は確かに愛の表れですが、行為そのものが愛であるとは限らず、また受け取る側の解釈によっても意味が変わります。
さらに、人は慣れる生き物です。毎日のように繰り返される親切や支えは、次第に「特別な出来事」から「日常の習慣」へと変質していきます。最初は胸が熱くなるような感謝を覚えても、やがては「そうしてくれて当然」とすら思ってしまう。その瞬間、愛は目の前に存在していながら「見えないもの」へと転じるのです。

3.「空気のような存在」としての愛
しばしば「愛は空気のようなもの」と形容されます。空気は普段意識されることはほとんどありませんが、もしもなくなれば、数分と生きられない存在です。愛も同じく、普段はその存在を忘れがちですが、失ったときに初めて深刻さを思い知らされます。
この比喩には二重の意味が込められています。ひとつは、愛が人間の生命を支える基盤であるということ。もうひとつは、その基盤の重要性が「見えにくい」ことにこそ問題が潜んでいるということです。
愛を空気にたとえるとき、私たちはしばしば「だから大切にしよう」と結論づけます。しかし実際には、空気のように“あって当然”と受け止める傾向こそが、人間関係に摩擦や歪みをもたらすのです。

4.「見えなくなった愛」が生む歪み
では、愛を当たり前とみなし、その存在を忘れてしまうと、人間の心にはどのような影響が及ぶのでしょうか。いくつかの側面から考えてみます。
① 感謝の喪失
愛を見えなくすることは、同時に「感謝を感じにくくなる」ことでもあります。親が毎日のように食事を用意してくれること、友人が気軽に声をかけてくれること、パートナーが黙ってそばにいてくれること。これらを「当然」と受け止めてしまえば、感謝の言葉は失われます。そして感謝のない関係は、いつしか義務感や不満に塗り替えられてしまいます。
② 愛情の一方通行化
相手が注いでくれる愛に気づかなくなると、自分もまたそれを返さなくなります。つまり「受け取るだけで返さない」状態が続き、関係は不均衡に傾いていきます。やがて相手は疲弊し、愛情表現そのものをやめてしまうかもしれません。
③ 心の飢餓感
皮肉なことに、愛を当たり前とみなす人ほど「自分には愛が足りない」と感じやすくなります。本当は十分に与えられているのに、その存在を見落としてしまうため、常に飢餓感に苛まれるのです。こうした感覚は自己肯定感を低下させ、人間関係に不満を募らせる悪循環を生みます。

5.なぜ人は「愛の不在」に敏感なのか
興味深いのは、愛が過剰にあるときよりも、欠けたときのほうが強烈に意識されるという点です。これは心理学でいう「ネガティビティ・バイアス」とも関連しています。人間はポジティブな出来事よりも、ネガティブな出来事に敏感に反応する傾向を持つのです。
そのため、日常の小さな愛情表現は見過ごされやすく、逆に無視されたり冷たくされたりすると深く傷つきます。結果として、「愛は欠けたときにのみ姿を現す」という逆説が成立してしまうのです。

6.「気づく力」をどう育てるか
では、どうすれば愛を「当たり前」として埋没させず、その存在を意識的に感じ取ることができるのでしょうか。ここで重要になるのが「気づく力」です。
① 小さな行為に目を向ける
愛は大げさな言葉や派手な行為だけで表れるものではありません。何気ない一言、沈黙の共有、相手が不機嫌なときに距離を保つことさえも、愛のかたちである場合があります。その小ささに気づけるかどうかが分かれ目になります。
② 日常を「記録」する
感謝日記のように、その日に受け取った小さな親切や嬉しかったことを文字にして残すと、見えなくなりがちな愛を再発見できます。文章にすることで、曖昧だった感覚が輪郭を持ち、愛の存在を実感しやすくなります。
③ 不在を意識する
逆説的ですが、意図的に「もし今これがなくなったら」と想像することも有効です。普段は気にも留めない家族の声、職場での何気ない会話、それがもし明日から消えてしまったら――そう考えることで、愛の存在がより鮮明に浮かび上がります。

7.愛の「当たり前」を問い直す社会的意義
ここまで個人レベルの話をしてきましたが、愛が当たり前に見えなくなる現象は、社会全体にも影響を与えています。
たとえば、地域社会における「助け合い」や「気遣い」は、以前は自然に行われていたものでした。しかしそれが「当たり前」とされるうちに感謝の意識が薄れ、今では多くの人が「他人に無関心」と批判する時代になっています。
また、企業や組織においても、従業員の献身や配慮が当たり前とされると、感謝の言葉は失われ、モチベーションの低下や人間関係の摩耗を招きます。社会のさまざまなレベルで、愛の「当たり前化」が歪みを生み出しているのです。

8.「愛を見える化する」試み
近年、「見えにくいものを可視化する」取り組みが盛んになっています。たとえば健康に関しては、運動量や睡眠の質を測定するデバイスがあります。同じように、愛に関しても「どれだけの愛情がやりとりされているか」を感じ取れる仕組みがあってもよいのかもしれません。
もちろん数値化することは難しいですが、愛を表す行為や言葉を積極的に記録し、共有することで、当たり前に埋没してしまう愛を「再発見」することはできるでしょう。

9.こう考える ― 愛を「呼吸」するように
「愛はなぜ“当たり前”になると見えなくなるのか」という問いに対して、私たちはまず「人は慣れる存在だから」という答えを出せるかもしれません。しかし、だからといって諦める必要はありません。慣れの中でも、意識的に気づき、感謝し、返していくことで、愛は再びその姿を現します。
愛を「呼吸」のように考えると分かりやすいでしょう。呼吸は普段意識しませんが、深呼吸するときに「生きている」ことを実感できます。愛も同じで、日常に埋もれながらも、ときおり意識的に立ち止まり、その存在を味わうことが大切です。
見えなくなった愛を再び見えるようにする。それは大げさに言えば、人間の心に生じる歪みを修復する第一歩でもあるのです。