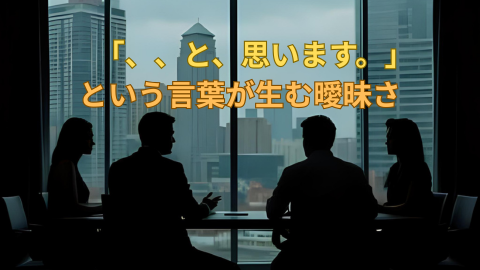
~「・・・と、思います」という言葉が生む曖昧さと信頼の揺らぎ~
はじめに
私たちが日常生活や職場でやり取りをするとき、言葉の使い方ひとつで受け手の印象が大きく変わることはよくあります。中でも「思います」という語尾の使い方は、特に日本語において独特のニュアンスを持っています。
報告や事実確認を求められた場面で、「〇〇です」と断定すべきところを「〇〇だと思います」と答える人が少なくありません。これを聞いた側は、「なぜ断定を避けたのか」「確信がないのではないか」「責任を持ちたくないのではないか」と、さまざまな解釈をしてしまいます。報告の正確性や信頼性を重んじる場面では、特にこの言葉遣いが問題になることがあります。
以下では、この「思います」という表現が持つ意味、なぜ使われるのか、それがもたらす影響、そしてどう付き合っていけばよいのかを考察していきたいと思います。

1. 「思います」の二重性
「思います」という言葉は、一見すると謙虚さや柔らかさを帯びています。断定を避けることで相手に考える余地を残し、対話の余白を広げる効果があります。そのため、日常会話や人間関係を円滑に保つ上では役立つ場面も少なくありません。
しかし一方で、「思います」は断定を避けるがゆえに、事実を伝えるべきシーンでは「不正確さ」や「無責任さ」と受け取られやすい言葉でもあります。報告という行為は、聞き手に判断材料を提供するために行われます。その情報が「事実なのか」「推測なのか」が不明確なまま伝えられると、結果的に判断の誤りや信頼関係の揺らぎにつながる可能性があります。
つまり「思います」は、和を重んじる日本文化の中で多用されながらも、場面によっては不適切に響いてしまう、両義的な言葉なのです。

2. なぜ「思います」をつけてしまうのか
では、なぜ人は事実を伝えるときでさえ「思います」を付け足してしまうのでしょうか。いくつかの理由を挙げてみます。
(1) 責任回避の心理
もっとも大きいのは「責任を取りたくない」という心理です。もし「〇〇です」と断定して間違っていた場合、自分の責任が問われる可能性があります。そこで「思います」を付けることで、「あくまで自分の認識ではそうだが、違っていたら仕方ない」という逃げ道を残してしまうのです。
(2) 謙虚さや丁寧さの表現
日本語は断定を和らげる表現が多く存在します。「〜かもしれません」「〜でしょう」「〜と思います」などがその代表です。これらは謙虚さを示すための常套句であり、ビジネスシーンでも「です」と断定するよりも角が立たない、と考える人は少なくありません。
(3) 自信の欠如
単純に自分の知識や判断に自信が持てない場合もあります。断定する勇気がなく、「思います」というクッションを挟むことで心理的な安心を得ているのです。
(4) 習慣化された口癖
深く考えず、単なる口癖として「思います」を付けているケースもあります。特に学生や若手社員に多く見られ、プレゼンやスピーチでも無意識に多用してしまうため、「頼りなく聞こえる」と評価されてしまうことがあります。

3. 「思います」がもたらす影響
「思います」という言葉が悪いわけではありません。しかし、報告や説明の場面では次のような影響を及ぼします。
(1) 信頼性の低下
例えば医師に「この薬でよくなると思います」と言われたらどう感じるでしょうか。確かに医療に絶対はありませんが、「思います」がつくだけで患者は不安になります。ビジネスにおいても「契約は成立すると思います」と言われれば、確証がないように受け止められます。
(2) 判断ミスを誘発
報告を受けた側は「事実」と思って判断することもあります。しかし実際は発言者が曖昧な認識しか持っていない場合、判断を誤り大きな損失を生む危険があります。
(3) 発言者自身の評価への影響
「思います」を多用すると、発言者は「自信がない人」「責任を持たない人」と見なされがちです。特にリーダーや専門家の立場であれば、この評価は致命的になりかねません。

4. 「思います」を使うべき場面と避けるべき場面
すべての「思います」を否定する必要はありません。重要なのは「使い分け」です。
- 使うべき場面
- 意見や感想を述べるとき(例:「私はこの案が有効だと思います」)
- 謙虚さを示したいとき(例:「少し時間がかかると思います」)
- 相手の考えを尊重したいとき
- 避けるべき場面
- 事実報告を求められたとき(例:「本日、商品は届きました」)
- 根拠に基づいた説明をするとき(例:「調査の結果、この方法が最適です」)
- 責任ある立場で断定が必要なとき
つまり「事実」や「根拠」が求められるときには「思います」を外し、「意見」や「予測」のときには活用する。この線引きが重要になります。

5. 受け手の側ができること
とはいえ、相手が無意識に「思います」を多用する人であれば、受け手としてどう対応するかも大切です。
- 確認を入れる
「それは事実ですか? それとも推測ですか?」と聞くことで、相手の発言を明確にすることができます。 - 安心感を与える
相手が責任を恐れている場合、「間違っていても構わないので、現時点で分かる範囲を教えてください」と伝えると、断定しやすくなることがあります。 - 教育や指導
職場であれば「報告では断定形を使うことが基本」とルールを明確に伝えることが有効です。

6. 自分自身の言葉をどう磨くか
「思います」の問題は、相手の言葉遣いに気づいた人が不安や不満を抱くことから始まります。しかし逆にいえば、自分自身も無意識に同じような言葉遣いをしている可能性があります。
自分の発言を振り返り、「ここは事実なのか、意見なのか」を意識して言葉を選ぶ習慣をつけることが大切です。特に人前で話すときや文章を書くときは、断定と曖昧表現のバランスを意識するだけで、伝わり方が大きく変わります。

まとめ
「思います」という言葉は、便利で柔らかい響きを持ちながら、場面を誤ると報告の正確性や信頼を損ねるリスクをはらんでいます。特に報告や説明といった「事実伝達」の場面においては、断定を避けた言葉遣いが相手に誤解や不安を与えます。
一方で、「思います」は人間関係を和らげ、謙虚さを示すための重要な表現でもあります。要は「場面に応じてどう使い分けるか」に尽きるのです。
受け手の側も、ただ不快に感じるだけでなく「確認」「教育」「安心感の提供」を通じて、相手が正確に表現できるようにサポートすることができます。そして何より、自分自身が言葉を選ぶ際に「事実か、意見か」を意識することが、信頼される発信者への第一歩となるでしょう。

言葉は単なる音や文字ではなく、人と人との間に信頼や不信を生む「橋」です。「思います」の使い方ひとつをきっかけに、私たちは改めて言葉の力を見つめ直す必要があるのではないでしょうか。
