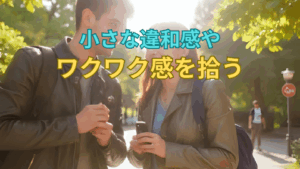ー自己実現と他者貢献の交差点ー
「やりたいことは何ですか?」と問われたとき、多くの人は自分の夢や目標、好きな活動を思い浮かべます。音楽をやりたい、絵を描きたい、旅をしたい、スポーツで活躍したい――それらは一見するとすべて「自分のため」の欲求に見えるかもしれません。しかし、よく考えてみると、本当に「やりたいこと」は必ずしも自分中心のものではなく、むしろ「誰かの役に立つ」「人に喜んでもらえる」経験を通じて芽生えることが多いと思います。
つまり、自己実現と他者貢献は決して対立する概念ではなく、むしろ深く結びついています。同様な内容の投稿は何度かさせて頂いておりますが、今回は、その交差点にある価値について考えてみたいと思います。

1. 「やりたいこと」の源泉をたどる
人が「やりたい」と感じる動機の奥には、必ず何らかの「体験」が存在します。例えば、子どもの頃に家族に料理をふるまって「美味しい!」と喜ばれた体験が、料理人を目指す原点になることがあります。あるいは、病気で苦しんでいたときに医師や看護師に支えられた経験が、「自分も医療で人を支えたい」という想いに変わることもあります。
つまり、「やりたいこと」は単なる自己満足ではなく、「誰かとの関わり」の中で育まれていることが多いのです。自己実現の裏には、ほとんどの場合「他者から与えられた喜びや救い」が潜んでいます。

2. 「誰かのために」が持つ力
心理学の勉強の中で、利他的行為が自己の幸福感を高めることが繰り返し示されています。小さな親切でも、誰かに「ありがとう」と言われると、心が温かくなる経験は多くの人に共通しているでしょう。このとき、相手が受け取ったものは物質的には小さくても、心の交流が「自分の存在価値」を強く実感させてくれるのです。
さらに、他者に貢献することで生まれる「役に立っている感覚」は、自己肯定感を支える大きな要素となります。自分の力が他人の生活や心を少しでも支えていると気づいたとき、人は「生きていてよかった」と感じるのです。

3. 自己実現と他者貢献の交差点
「自己実現」は一般に、自分の夢や目標を達成することだと考えられています。しかし、もしその夢や目標が「誰かのためになるもの」であれば、それは同時に他者貢献でもあります。
たとえば、音楽家が「自分が心からやりたい音楽を表現する」ことは自己実現ですが、それを聴いた人が癒されたり勇気づけられたりすれば、同時に他者貢献にもなっています。教師が「自分の知識を伝えたい」という自己実現を行うことで、子どもたちが学び成長すれば、それは確かな社会的貢献です。
自己実現と他者貢献は「別物」として対立するのではなく、むしろ「交わる地点」において最も大きな価値を生み出すのだと言えるでしょう。

4. 「誰かのため」が生み出す新しい「やりたいこと」
多くの人は、「やりたいことを見つけたい」と思いながらも、自分の中に答えを探そうとしがちです。しかし実際には、自分の内側だけを探しても見つからない場合があります。そのとき有効なのは、「誰かのためにできること」に目を向けてみることです。
ボランティア活動に参加して人の笑顔を見る、困っている友人を助けて感謝される――そんな体験から「もっと人を支える活動をしてみたい」という新しい「やりたいこと」が生まれるのです。つまり、「やりたいことは他者との関わりの中で発見される」可能性が高いのです。

5. 「自分中心」と「他者中心」のバランス
ただし、他者貢献を強く意識しすぎると、「人のために生きなければならない」というプレッシャーに変わることもあります。その結果、自分自身を犠牲にして燃え尽きてしまう人も少なくありません。
大切なのは、「自分が楽しみながらできることを通じて誰かを幸せにする」というバランスを保つことです。無理に自分を抑え込んで人のために尽くすのではなく、「自分にとって心地よい範囲で、誰かの役に立つ」関わり方を見つけることが、持続可能な他者貢献につながります。

6. 小さな一歩から始める
「誰かのためにできること」というと、大きな活動や社会的な貢献を思い浮かべるかもしれません。しかし、日常の中でできる小さなことも立派な貢献です。
・電車で席を譲る
・道に迷っている人に声をかける
・ちょっとしたお礼を言葉にする
・自分の得意なことで友人を助ける
これらはすべて、誰かの心に温かさを残します。そして、その積み重ねは自分にとっても「自分は役に立てている」という実感をもたらし、やりたいことの新しい芽を育むのです。

7. 社会全体に広がる可能性
もし一人ひとりが「自分のやりたいこと」と「誰かのためにできること」を重ね合わせて生きるようになったら、社会全体の雰囲気は大きく変わるでしょう。競争や自己利益の追求だけでなく、互いに支え合う空気が自然に生まれ、結果として社会の幸福度も高まります。
他者貢献を無理なく楽しみながら行える人が増えることは、社会にとって最も健全な成長の形ではないでしょうか。

8. 結びにかえて
「やりたいこと」は必ずしも自分だけの欲望から生まれるわけではなく、むしろ「誰かの役に立つ経験」から芽生えることが多い。そう考えると、自己実現と他者貢献は互いに補い合いながら成長していくものだと言えます。
大きなことをしなくても、日々の生活の中で「誰かのためにできる小さなこと」に気づき、実行してみる。その積み重ねが「本当にやりたいこと」を見つけるヒントになり、やがては自分自身の人生を豊かにし、同時に誰かを支える力となるのです。