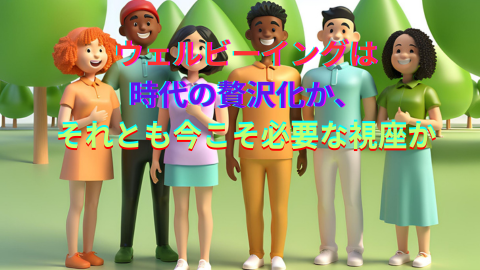
ウェルビーイングへの関心低下をめぐる現状と背景
――なぜ私たちは「幸せ」を語りづらくなっているのか――
はじめに
近年、個人や社会の「より良い状態」を目指す概念として注目されてきた「ウェルビーイング(well-being)」。幸福や生きがい、心身の健康、社会とのつながりなど、多面的な要素を内包するこの概念は、本来、時代や立場を超えて普遍的な意義を持つものです。しかし現在、その普及の勢いには陰りが見え始めています(個人的見解で、その様に感じております)。なぜ今、ウェルビーイングのモチベーションが下がっているのか。その背景を読み解くために、以下の三つの視点から考えてみたいと思います。

1. ブームとしての「消費」がもたらす表層化
日本社会では、新しい価値観や理念が登場すると、それが「ブーム」として一気に注目される傾向があります。SDGs(持続可能な開発目標)やESG投資なども、当初は広く話題を集めた一方で、その後、深い理解や実装を伴わないままフェードアウトしていく例も少なくありません。ウェルビーイングも、同様の運命を辿っているように見受けられます。
企業においては、「ウェルビーイング経営」といった言葉が打ち出され、福利厚生の一環として一時的に取り入れられたものの、具体的な効果測定や従業員の実感との乖離が指摘され、単なる流行語に終わってしまうケースも見られます。このような表層的な取り組みは、かえって人々に「またか」「中身がない」という印象を与え、真の意味でのウェルビーイングの価値を損ねかねません。
2. 政治的・社会的緊張の影響
もう一つの大きな要因として、世界的な政治・社会の緊張状態が挙げられます。特に2016年のトランプ大統領の登場以降、アメリカをはじめとする先進諸国では、リベラリズムに対抗する形でポピュリズムやナショナリズムが台頭し、分断と対立の構図が鮮明になってきました。また、本年(2025年)一月のトランプ大統領の再就任により、世界の情勢が再度変わってきつつあります。
くわえて、ロシアによるウクライナ侵攻や中東地域の長期的な紛争といった国際的な不安定要因が、私たちの日常にもじわじわと影を落としています。こうした状況下では、人々の関心は「自己実現」や「社会とのつながり」といった成熟社会的な価値から、「生活の安定」「身の安全」へとシフトしやすくなります。
不確実性の高まる社会において、「ウェルビーイング」は一種の「余裕のある社会の話」として後回しにされがちです。しかし本来、こうした時代だからこそ、心の安定や人との信頼が問われるべきであり、ウェルビーイングの再定義が求められているのかもしれません。

3. コロナ後の社会の再編成フェーズ
さらに忘れてはならないのが、コロナ禍という未曾有の危機がもたらした社会の大きな変化です。感染症の拡大を契機に、リモートワークやオンライン化が進行し、人と人との距離感やコミュニケーションの在り方が大きく揺らぎました。
その過程で、人間関係や働き方、居場所の感覚が再構築される中、多くの人が「とりあえず今を乗り切ること」に精一杯になっています。価値観がまだ定まらず、混乱と適応の狭間にある今の社会では、「自分らしく幸せに生きる」といった問いが、やや遠いものに感じられてしまうのも無理はありません。
ウェルビーイングの実現には、自分自身の内面と向き合う時間と、安心して語れる環境が必要です。しかし、社会全体が再編成の只中にある現在、その前提が整っていない可能性もあります。

おわりに
ウェルビーイングという概念は、単なる流行や装飾的な施策ではありません。むしろそれは、「どうすれば私たちは幸せに生きられるのか」という、時代を超えた根本的な問いに対する探求です。今、モチベーションの低下が見られるのは、必ずしもウェルビーイングが不要になったからではなく、それを考え、実践するための社会的・心理的余白が一時的に失われているからではないでしょうか。
私たち一人ひとりが、表面的な取り組みを越えて、ウェルビーイングを再び「自分ごと」として捉え直すこと。そのための対話や場づくりこそが、これからの社会に求められているものだと考えます。

