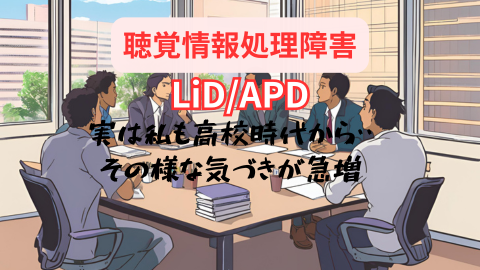
聴覚情報処理障害(Auditory Processing Disorder: APD)とは、「聞こえている」のに、「聞き取れない」、「聞き間違いが多い」など、音声をことばとして聞き取るのが困難な症状を指します。通常の聴力検査では異常が発見されないこの症状は、耳から入った音の情報を脳で処理して理解する際に、なんらかの障害が生じる状態だと考えられています。
この状態を表す言葉として、海外ではListening difficulties:LiDという言葉が使用されることが多くなっています。私たちはこのLiDを「聞き取り困難症」と称し、従来のAPDをLiD/APDとして表記していくことにしました。
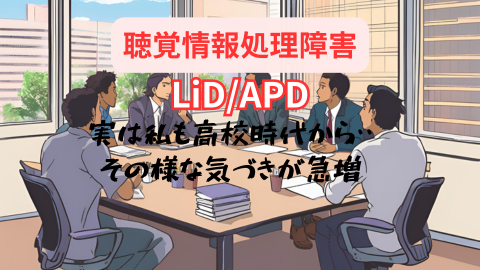
LiD/APDへの認知の変遷
こうした症状に対する研究は1950年頃から欧米を中心にはじまり、診断・支援に関して各国でガイドラインが作成されました。しかし、LiD/APDの発見は比較的新しいため明確な治療法はまだ確立されていません。早急な疾患概念の整備と診断基準の作成が求められているのが現状です。
欧米に比べて日本での認知度ははるかに低い状況ですが、一方では研究が進みつつあります。近年、LiD/APDが小児の言語発達の遅れの原因の一つであることや、欧米で言われる聴覚のみの障害ではなく、発達面の問題を抱える例が多く存在することが指摘されてきました。また、NHKニュースでLiD/APDが取り上げられたことをきっかけに症例が広く知られるようになり、幅広い年代の人達が診断を求めるようになりました。(以上、『当事者ニーズに基づいた聴覚情報処置障害診断と支援の手引きの開発』ホームページより引用)←我々が日常生活で聞こえている状態の音声がアップされていますので、ぜひご確認ください。

聴覚情報処理障害(APD)とは?
聴覚情報処理障害(APD:Auditory Processing Disorder)は、耳の聴力自体には問題がないにもかかわらず、音(特に言葉)の処理や理解に困難を感じる障害です。具体的には、以下のような症状があります。
- 雑音が多い環境では会話が聞き取りづらい
- 早口や小さな声が理解しにくい
- 似た音の区別がつきにくい(例:「さ」と「た」、「パ」と「バ」)
- 指示を一度で理解するのが難しい(特に長い指示)
- 文字を読むより聞くほうが疲れる
APDは知能や学力とは関係がなく、環境や状況によって困難の程度が変わることが特徴です。そのため、周囲に理解されにくいことが多く、「聞いていない」「注意力が足りない」と誤解されがちです。私の経験ですが、特にマスク着用の会話は気をつけなければいけません。

APD患者が増えている理由とは?
APDの認知度が上がり、診断されるケースが増えていることも一因ですが、それに加えて以下のような要因が考えられます。
① デジタル環境の影響
近年、子どもから大人までスマホやタブレットの使用時間が増加し、会話や音声による情報処理の機会が減っている可能性があります。
特に、動画視聴の増加によって「文字で補助される情報」に依存しがちになり、聴覚情報だけでの処理能力が育ちにくいという指摘もあります。
② マスク社会の影響(コロナ禍以降)
マスクの着用により口元が見えない状態が続いたことは、特にAPD傾向のある人にとって厳しい環境でした。
通常、人は口の動きや表情をヒントにして音を理解しますが、それができない状況が長引いたため、「聞き取りづらさ」に気づく人が増えたのかもしれません。
③ 騒音の多い環境での生活
都市部では、カフェ、職場、交通機関などのBGMや環境音が増えていることも関係するかもしれません。APDの方にとって、複数の音が重なる環境は情報の処理を難しくするため、「聞こえているけど、意味が分からない」状態が生じやすくなります。
④ ストレスや過労による影響
過度なストレスや疲労は、脳の情報処理能力を低下させることが分かっています。現代社会では多くの人が仕事や生活のプレッシャーを抱えており、特に働き盛りの世代や学生において、APDの症状が顕在化しやすくなっている可能性があります。
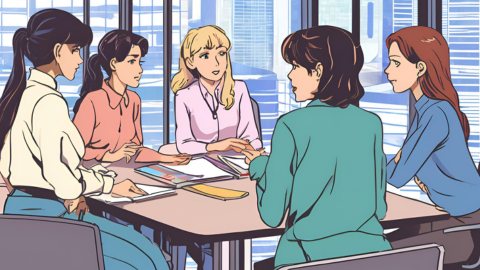
私見:APDと社会の関係性について
私は半世紀ぐらいこの病気と向き合いながら過ごしてきた事になりますが、最近になって診断が増えていることについて、私もそうですが、「APDが増えた」のではなく、「気づく人が増えた」のではないかと考えています。
以前は、「聞き取りにくさ」は個人の能力の問題とされ、障害とは認識されにくかった。しかし、今は情報が広がり、共感できる体験談を共有できる場が増えたことで、ようやく「これが自分なんだ」と確信を持つ人が増えているのでしょう。
APDのある人が生きやすい社会にするには?
- 「聞こえていない」のではなく、「処理しづらい」だけと周囲が理解する字幕や文字情報の充実(例:会議の音声文字起こし、授業のスライド活用)
- 話し方の工夫(ゆっくり話す、短く区切る)
- 聴覚処理の負担を減らす環境づくり(静かなスペースの確保)
APDのある方々がより暮らしやすい環境を作ることは、結果的に社会全体の「聞く力」や「伝える力」を高めることにつながると思います。

生きづらい社会と感じる人が一人でも減っていく事こそ、しあわせと感じる人が増えていく道しるべになるのではないでしょうか。

