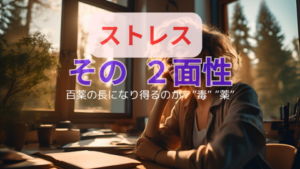「幸福中心社会への転換」は、世界的な潮流になりつつあると思います。特に近年、GDPや経済成長だけでなく、人々の幸福度やウェルビーイングを社会の指標とする動きが広がっています。この流れを象徴するものとして、いくつかのトレンドが挙げられます。
1. 政策・社会構造の変化
- ブータンのGNH(国民総幸福)をはじめ、ニュージーランド、フィンランド、カナダなどでは、幸福度を基盤とした政策が推進されています。
- 国連の「世界幸福度報告」が注目され、国際的にも幸福度が重要な指標として扱われるようになっています。
- 「ウェルビーイング経済連合(WEAll)」といった新たな枠組みが台頭し、経済成長と幸福のバランスを取る動きが進んでいます。
2. 企業・ビジネスの価値観の変化
- 従業員の幸福(Employee Well-being)が企業経営において重要視され、Googleやパタゴニアのような企業は、単なる利益追求ではなく、働く人の満足度向上を目指す経営を進めています。
- サステナビリティ(ESG経営)の文脈でも、「人間中心の社会」が求められ、従来の経済成長至上主義からのシフトが起きています。

3. 個人の価値観の変化
- ミレニアル世代やZ世代は、「成功=高収入」ではなく、「成功=充実した人生」と捉える傾向が強く、ワークライフバランスや社会貢献を重視する生き方を選ぶ人が増えています。
- 「タイニーハウス」や「ミニマリズム」など、物質的な豊かさよりも精神的な豊かさを重視するライフスタイルもトレンド化しています。
4. 科学的な裏付け
- ポジティブ心理学の発展により、幸福の要素(人間関係、感謝、マインドフルネス、利他性など)が科学的に証明され、それを実践しようとする人が増えています。
- 幸福経済学の研究が進み、「お金が幸福をもたらすのはある程度まで」「幸福度が高い社会のほうが生産性も上がる」といった知見が広まりつつあります。

私達はこの流れをどのように活かせるか?
「幸福中心社会への転換」がトレンドであるならば、4月のイベント『令和の幸せ/つながる』において、その流れを具体的に体験できる場として考えております。特に以下のような視点を強調し、時代に合ったメッセージを伝えたいと思います。
- 「幸せ=つながり」
→ 個人の幸福と社会とのつながりをリンクさせることで、幸福の循環を意識できるようにしたい。 - 「幸せの主体は自分」
→ 企業や政府に頼るのではなく、一人ひとりが自分の幸福について考え、実践することの重要性を伝える。 - 「幸せは広がるもの」
→ 利他的な行動が自分の幸福にもつながるという心理学的な知見を活かし、「幸せを広げる行動」の重要度を伝える。

●「幸福中心社会への転換」は、一過性の流行ではなく、世界的な価値観のシフトとして定着しつつあります。その中で、『令和の幸せ/つながる』というテーマは非常にタイムリーであると思っておりますが、「単なる理想論」にならないよう、具体的なアクションや実践的な考え方を提示することも重要と考えております。
① 参加者が「幸せのアクション」を体験できる場を作る
② 「つながり」を生み出し、継続できる仕組みをつくる
③ 「社会への波及効果」を意識したメッセージを発信する
④ 「幸せを生み出す循環」のための資金の仕組みをつくる
以上の様なアプローチの具体的な提案も公開したいと考えています。

さらには、幸福度が社会に与える影響は様々なデータがございます。例を挙げておきます。
1. 幸福度と労働生産性の関係
幸福度が高まると労働者の生産性が向上することが、さまざまな研究で示されています。
- ニッセイ基礎研究所の実験結果
ニッセイ基礎研究所が独自に実施した大規模WEB実験では、幸福度が高まると労働者の生産性が向上するという因果関係が実証的に示されています。 nli-research.co.jp - OECD諸国のデータ分析
OECD諸国の幸福度と1時間あたりの労働生産性の関係をプロットした結果、正の相関関係が確認されています。 nissay.co.jp
2. 幸福度と地域社会の安全性の関係
幸福度が高い地域ほど、犯罪率が低いというデータも存在します。
- 内閣府の「満足度・生活の質に関する調査」
内閣府が実施した調査では、地域のつながりやコミュニティへの参加が高い地域ほど、住民の満足度が高く、結果として地域の安全性が高まる傾向が示されています。 www5.cao.go.jp

3. 幸福度と健康寿命の関係
幸福度が高い人は、健康寿命が長いことも報告されています。
- 野村総合研究所の調査
野村総合研究所が2023年2月に実施した「日本人の生活に関するアンケート調査」によれば、幸福度が高い人ほど健康状態が良好であり、健康寿命が長い傾向が見られます。 nri.com
まとめ
これらのデータから、幸福度の向上が個人の生産性や地域社会の安全性、さらには健康寿命の延伸に寄与することが示されています。したがって、幸福度を高める取り組みは、個人だけでなく社会全体にもポジティブな影響をもたらすと考えられます。