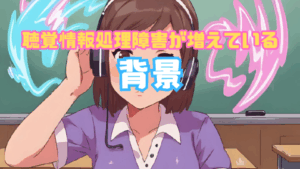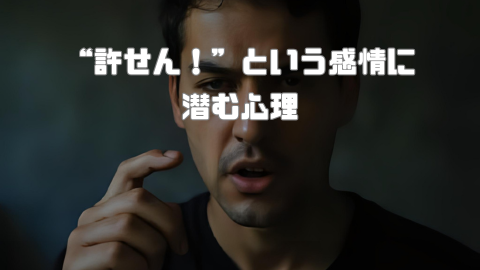
ー求めすぎる人間関係の落とし穴ー
あるプロ野球選手が引退セレモニーを迎えた際のことです。
彼の長年の功績を讃える場に、かつての仲間や後輩たちから多くのビデオメッセージが寄せられました。しかし、その中に世界的に活躍するメジャーリーガーの後輩からのメッセージがなかったことを理由に、本人が「アイツは許せん!」と怒りをあらわにした――そんな報道がありました。
そして本人は複数のメディアでも同様の発言を繰り返し、その後、古巣からの強制トレード、結果出ず、さらなるトレード、出番激減、そして引退という道をたどることになります。
この一連の出来事をどう見るか。
「小さなことを気にしすぎだ」と片付けることもできるかもしれません。しかし、そこには多くの人が陥りやすい“心理の構造”が隠れています。つまり、「認められたい」「大切にされたい」という承認欲求が、理性を超えて暴走してしまう瞬間です。

■「送ってくれて当然」という心理の罠
本来、ビデオメッセージとは相手が自らの意思で贈るものであり、求めて得るものではありません。しかし、この選手の中では「自分はその後輩をかわいがってきた」「多くの人が送ってくれているのだから、彼も当然送るべきだ」という“当然の期待”が生まれていたのでしょう。
以前に何度も書きましたが、心理学でいう「規範的期待」や「対人スキーマ」という考え方があります。
私たちは人間関係の中で、「こうあるべき」「こうしてくれるはず」という無意識のルールを持っています。それが裏切られると、まるで自分の存在を否定されたかのように感じてしまうのです。特に年長者や地位のある人ほど、その“自分なりのルール”が強固になりやすい傾向があります。
この「当然」の基準は、本人にとっては自然であっても、他者にとってはそうではありません。
つまり、「送ってこなかった後輩」ではなく、「送ってくるのが当然だと信じた自分」が怒りを生んでいるのです。現在の相手の立場がうんぬんかんぬんではありません。

■「許せない」の正体は、傷ついた自尊心
「許せん!」という言葉の裏には、実は“悲しみ”があります。
心理学的に見ると、怒りは二次感情と呼ばれるもので、一次的には「寂しさ」や「失望」などの感情が存在しています。
つまりこの選手は、「自分は軽んじられた」「あいつはもう自分を必要としていない」という寂しさを、怒りという形で表現してしまったのでしょう。
特に引退という“社会的役割を失う瞬間”を迎える時、人は自分の価値を再確認したくなります。
その時、他者からの“尊敬”や“感謝”が支えとなる一方で、それが欠けると心のバランスが崩れやすくなるのです。
心理学では、こうした心の動きを「自己価値の維持メカニズム」と呼びます。
自尊心が脅かされると、人はそれを守るために他者を非難したり、相手の落ち度を探したりする行動に出やすくなります。
彼の「許せん!」という言葉は、実は「自分はまだ価値のある存在だ」と叫ぶ、最後の自己防衛でもあったのかもしれません。

■人間関係における“貸し借り”の錯覚
長い人生の中で、人は「自分はこれだけしてきたのだから、相手も応えてくれるはずだ」という“心理的な貸し借り”を感じることがあります。
この構造は、心理学では「互恵性の原理」と呼ばれるという事です。
本来は人間関係を円滑にするための自然な社会的ルールなのですが、これが強くなりすぎると、いつしか「見返りを期待する関係」に変わってしまいます。
とくに年齢や立場の差がある関係では、この互恵性のバランスが崩れやすくなります。
“与える側”が多かった人ほど、「自分の善意が報われなかった」と感じたときの落胆は大きいのです。
しかし本来の成熟した関係とは、“与えて終わり”の関係です。
見返りを求めず、相手の成長や自由を認める――それができたとき、人は本当の意味で他者を尊重していると言えるのではないでしょうか。

■メディアで語るという“自己顕示の罠”
この選手の問題は、怒りを感じたことそのものよりも、それを公の場で何度も語った点にあります。
本来なら心の中で整理すべき感情を、メディアを通して表現してしまった背景には、「他者から共感を得て自分を正当化したい」という心理があります。たとえサービストークであったとしても発言すべきでは無いと思うのです。
これはSNS時代にも通じる構図です。
私たちは誰かに不満を持つと、つい「わかってほしい」「味方してほしい」と外に発信してしまいます。
しかし、怒りの発信は一時的なスッキリ感を与える一方で、他者の心には“未熟さ”や“自己中心性”という印象を残します。
本人の意図とは裏腹に、結果として自らの評価を下げてしまうのです。

これも何度も書きましたが、「認知的不協和理論」によれば、人は“自分の行動と信念が矛盾した状態”を強い不快として感じます。
この選手も、「立派なプロ野球人生を送りたい」という信念と、「後輩を許せない」という感情の矛盾を抱えていたはずです。
その不協和を解消するために、彼は「後輩が悪い」と公に語ることで、自分の行動を正当化しようとした――そんな心理的メカニズムが働いていたと考えられます。反面、ご自分の人間的評価を半ば周囲に周知されているレベルから、さらに落としていることには全く気が付いていないと思います。
しかしながら、以上書いてきましたが報道されている内容だけで判断をしていますので彼の真意は不明です。ですので、一般的にもそのようなパターンがあるという事でご理解をお願いいたします。

■成熟とは、「期待しない優しさ」を持つこと
人間は誰しも、誰かに感謝されたい、認められたいという欲求を持っています。
それは決して悪いことではありません。むしろ、人とのつながりを求める自然な心の働きです。
しかし、人生の後半に差しかかるほど、私たちが学ぶべきは“手放すこと”です。
「相手がどう思おうと、それはその人の自由」と受け止められるようになること――それが人間的成熟のひとつの形です。
もし、あの選手が「まあ、忙しいんだろうな。彼の成功を嬉しく思うよ」と笑って受け流せたなら、彼の最後の舞台はもっと清々しいものになっていたでしょう。
そして、その姿勢こそが、後輩たちに最も深く記憶される“引き際の美学”だったのではないでしょうか。

■「許せん!」を「ありがとう」に変える力
私たちは日々、小さな「許せない」に直面しています。
約束を忘れた友人、感謝を伝えない同僚、思うように動いてくれない家族……。
しかし、そうした出来事の多くは、相手の悪意ではなく「期待のずれ」から生まれるものです。

他者に完璧を求めず、「自分がどうありたいか」に意識を向ける。
怒りを手放し、受け入れる心を持つことで、人間関係は驚くほど軽やかになると思うのですね。。
“許せん!”の一言を飲み込み、“ありがとう”に変える――。
それができたとき、人は本当の意味で「人としてのステップアップ」になるのではないでしょうか。