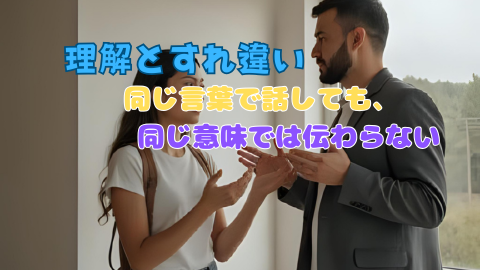
~同じ言葉で話しても、同じ意味では伝わらない~
親子ほど、近くて遠い関係はないのかもしれません。
同じ家で暮らし、同じ食卓を囲み、似た言葉で会話をしていても、「伝わらない」と感じる瞬間があります。
それは単なる世代の違いではなく、言葉の背後にある“意味”や“前提”が異なっているからなんですね。
つまり、同じ言葉を使っていても、互いが見ている世界が少しずつ違うのです。
多くの子を持つ親が共通で体験することから、社会生活においても通じる「学ぶべきこと」を考えたいと思います。

■「正しさ」がすれ違いを生むとき
親は、子どもが幸せになってほしいと願うものです。
だからこそ、「こうすべき」「これが正しい」といった言葉を口にします。
そこには経験に裏打ちされた思いやりがあります。
しかし、その“正しさ”が、時に子どもには“押しつけ”として届いてしまうことがあります。
たとえば、「安定した職に就いたほうがいい」という言葉。
親の世代にとっては、景気の波を乗り越え、家庭を守るための知恵でした。
けれど、現代の子どもたちは「安定よりも、自分らしく働くことに価値がある」と考える傾向が強い。
その結果、親のアドバイスが「時代遅れ」「古い価値観」と受け取られてしまうこともあります。
この“価値観のズレ”が、理解の溝を深めていきます。
親は「正しいことを言っているのに、なぜ分かってくれないのか」と感じ、子どもは「自分の気持ちを分かってもらえない」と心を閉ざす。
どちらも悪意はないのに、会話が噛み合わないのです。

■ 言葉の“温度差”という見えない壁
会話のすれ違いには、言葉の“温度差”も影響します。
親は「心配だから言っている」と思っていても、子どもは「信じてもらえていない」と受け取ってしまう。
同じ言葉でも、発する側と受け取る側では、温度がまるで違うのです。
たとえば、親が「もっと頑張りなさい」と言うとき。
そこには「あなたならできる」という励ましの気持ちがこもっているかもしれません。
しかし、子どもにとっては「今の自分ではダメだ」と否定されたように聞こえることがある。
結果として、「言えば言うほど伝わらない」という悪循環に陥ってしまうのです。
この“温度差”の原因は、互いの立場の違いにあります。
親は「過去から今」を見ており、子どもは「今から未来」を見ている。
親の言葉は“経験”に基づいていて、子どもの言葉は“理想”に向かっています。
だから、話す方向が微妙にずれてしまうのです。

■ 「分かってもらう」より「分かろうとする」
親子の対話で最も難しいのは、「分かってもらう」ことを求めすぎることかもしれません。
「なぜ理解してくれないの?」という思いが強くなるほど、対話はかえって遠のきます。
理解は“結果”であって、“目的”にしてしまうと苦しくなるのです。
大切なのは、「分かろうとする姿勢」を持ち続けること。
たとえ完全に分かり合えなくても、「この人は分かろうとしてくれている」と感じるだけで、心は少しずつ開いていきます。
それは“理解”というよりも、“共感のプロセス”と呼ぶべきものです。
子どもの言葉がたとえ極端に聞こえても、「どうしてそう思うの?」と尋ねるだけで、会話の空気は柔らかくなります。
親が自分の意見を一歩引いて、相手の言葉の“背景”を聞こうとすることで、単なる言葉のやり取りから、心のキャッチボールへと変わっていきます。

■ 「沈黙」もまた、対話の一部
すれ違いが深まると、どちらかが沈黙を選ぶことがあります。
しかし、その沈黙を「拒絶」と捉えるのは間違いと思うのですよね。
沈黙には、“自分の中で整理したい時間”という意味もあるからです。
たとえば、思春期の子どもが口を閉ざすとき。
それは、言葉が出ないほど心が揺れているからかもしれません。
あるいは、親の言葉にどう返せばいいか分からないだけかもしれません。
沈黙の裏には、まだ言葉にならない“感情”が隠れています。
それを見逃さないことも、理解の第一歩です。
そして、親が沈黙する場合もあります。
「何を言っても響かない」と感じたとき、人は自然と口を閉ざします。
けれど、その沈黙には「待つ」という意思が含まれていることもある。
「今は言葉が届かなくても、いつか届くかもしれない」と信じているからこその沈黙。
その静かな祈りこそ、親の愛情の形のひとつなのだと思います。

■ 「世代間の翻訳」という考え方
親と子のすれ違いは、ある意味では“異なる言語の間での誤訳”のようなものです。
同じ日本語を使っていても、その意味するところは微妙に異なります。
そこで大切になるのが、「翻訳する力」です。
たとえば、子どもが「もっと自由に生きたい」と言うとき、それは「親の価値観を否定したい」わけではなく、「自分の足で歩いてみたい」という表現かもしれません。
親がその“裏の意味”を訳して受け取れたら、無用な衝突は避けられます。
逆に、親が「心配している」と言うときも、子どもが「管理されている」と訳すのではなく、「大切に思われている」と翻訳し直すことで、関係は少しずつやわらぎます。
つまり、親子の対話には「世代間の通訳」が必要なのです。
そして、その通訳者は他でもない、当事者である“親子自身”なのです。

■ 「分かり合えないこと」を受け入れる勇気
すれ違いを完全に解消することは、実は不可能かもしれません。
なぜなら、親と子は異なる人生を歩み、異なる価値観を育ててきた個別の存在だからです。
完全に同じ景色を見られなくても、それは“失敗”ではありません。
むしろ、“違い”を前提にしながら、それでも関わり続けることが、成熟した関係の形ではないでしょうか。
親子の絆は、理解し合うことで深まるのではなく、“理解し合えないことを受け入れる”ことで穏やかに育っていくことがあります。
そこに必要なのは、諦めではなく、“余白”を持つこと。
相手を完全に理解できなくても、「それでも大切に思っている」という余白を残すことが、真の対話を生むのです。

■ 「わかろうとする勇気」が絆をつくる
親子の会話がすれ違うとき、私たちはつい“正しさ”で立ち向かおうとします。
けれど、関係をつなぐのは理屈ではなく、“心の姿勢”です。
「自分の考えを伝える勇気」よりも、「相手をわかろうとする勇気」のほうが、人と人との距離を近づける力を持っています。
たとえ今は理解し合えなくても、その姿勢がある限り、言葉はいつか届きます。
親子とは、人生の中で最も長い対話を続ける関係です。
だからこそ、一時のすれ違いに心を閉ざさず、「もう一度、相手の立場から見てみよう」と思える柔らかさを持ち続けたいものです。
同じ言葉で話しても、同じ意味では伝わらない。
それは人間の限界ではなく、関係を深める“余地”なのだと思います。
その余地を大切にしながら、親子という旅の途中で、少しずつ「わかり合う勇気」を育てていく――それが、時代を越えて変わらない、親と子の絆のかたちなのではないでしょうか。

