
過保護社会の副作用
「うちの子には失敗してほしくない」「危ない目にあわせたくない」。
この言葉に込められた親心を、誰が責めることができるでしょうか。愛情の根底には常に「守りたい」という本能的な感情があります。けれども、近年その“守りたい”という思いが、知らず知らずのうちに子どもの「生きる力」や「対人耐性」を奪っているのではないか——そんな懸念が社会全体で広がり始めています。
現代社会は、一見すると安全で便利です。しかし、その安全さと便利さが、人と人との関わりを減らし、体験から学ぶ機会を奪っている側面もあります。そこに親の“過剰な不安”が加わると、子どもが社会に出る前から、「リスクを取らない生き方」しか選べなくなってしまうのです。

■「不安社会」が育てた“過保護”という文化
かつての日本では、地域や近所とのつながりの中で、子どもは自然に多様な価値観や行動パターンに触れていました。近所のおじさんに叱られたり、友だちとケンカしたり、先生に怒鳴られたりすることも日常でした。そうした小さな摩擦や失敗の積み重ねこそが、「他者と折り合いをつける力」や「自分の立ち位置を理解する感覚」を育てていたのです。
しかし、時代が進むにつれて、社会全体が「不安」に敏感になりました。ニュースでは事件や事故が繰り返し報じられ、インターネットには危険情報があふれています。子どもが少しでも外でトラブルに巻き込まれたと聞けば、「うちの子には絶対そんな思いをさせたくない」と親は強く反応します。
こうして「子どもを危険から守る」ことが、親の当然の使命のように語られる時代になりました。けれども、その“当然”が積み重なると、子どもは「失敗しても大丈夫」という感覚を持つ機会を失っていきます。すべてが“安全なレールの上”で整えられると、人は挑戦を避け、未知の他者と関わることを怖れるようになるのです。
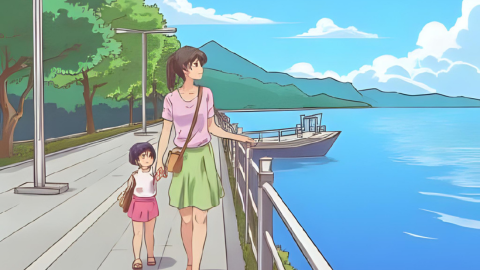
■「やさしい親ほど、子を不安にする」 paradox
心理学の観点から見ると、親の「やさしさ」は二つの顔を持ちます。
一つは、子どもが安心して自分を表現できるように支える“受容的なやさしさ”。
もう一つは、子どもの代わりに不安や痛みを取り除こうとする“介入的なやさしさ”です。
後者のやさしさは、一見すると愛情深く見えますが、子どもにとっては「自分では解決できない」という無力感を植えつけることがあります。たとえば、友人関係でトラブルが起きたとき、親が先に学校へ電話をしてしまう。あるいは、就職活動で子が悩んでいるときに、親が企業情報を調べ、応募書類の添削までしてしまう。
こうした行為は、短期的には子どもを救うかもしれません。しかし、長期的には「自分の人生の主導権を他人(=親)に委ねる」感覚を強化してしまうのです。
しかも、現代の親世代自身も、バブル崩壊やリーマンショックなど、社会の不安定さを肌で感じて育ってきた世代です。彼らは「安定」を何よりも尊ぶようになり、子どもにも「安全で確実な道」を歩ませたいという願いを抱く傾向が強い。つまり、親の“過保護”は、単なる性格的な問題ではなく、「社会不安の構造的な反映」といえるのです。
一方で、「自由に本人に決めさせている!」という、一見、放任しているように見える過保護も存在します。それも、子供は不安になり誰かの影響を受けやすくなると思います。本気で突き放す勇気も親は必要かと思います。

■「対人耐性の欠如」という現代的症状
こうして育った子どもたちは、社会に出た途端、他者との関わりの中でつまずきます。
上司の注意を“否定”と受け取り、同僚の一言に傷つき、グループ活動で意見を出せない。
最近では「他人と関わると疲れるから、できるだけ関わらないようにしている」という若者も増えています。
その背景には、“失敗耐性”だけでなく、“対人耐性”の低下があります。
つまり、人との摩擦を経験してこなかったために、「衝突しても関係は壊れない」「意見が違っても共存できる」という感覚が育っていないのです。
SNSの発達もこの傾向を後押ししました。オンライン上では、気の合う人とだけつながり、不快な意見はミュートやブロックで簡単に排除できます。そうした環境に慣れると、現実社会での“他者の存在の重み”に耐えられなくなってしまう。結果として、引きこもりや孤立が深刻化しているのです。

■「他者との関わりを避けてきた親世代」の影
興味深いのは、この問題が親子の間で“連鎖”していることです。
親自身もまた、地域社会のつながりが希薄化した時代を生きてきました。PTAや町内会といった「人と関わる場」に距離を置き、仕事や家庭の中だけで完結する生き方を選んできた人も多い。
つまり、「他者との関わり方に不安を抱いている親」が、同じように「関わりを避ける子」を育ててしまうのです。親の不安が、そのまま子どもの社会不安へと“世代交代”しているともいえます。
その結果、家族という“安心の殻”の中では平穏でも、外の世界に出ると極端に脆い若者が生まれる——これが現代の過保護社会の深刻な副作用です。

■「やさしさ」と「自立の促し」をどう両立させるか
では、どうすればこの悪循環を断ち切ることができるのでしょうか。
鍵となるのは、「やさしさ」と「自立の促し」のバランスです。
親がすべきことは、子どもを守ることではなく、“子どもが自分で守れるようにすること”です。
たとえば、失敗したときにすぐ助けるのではなく、「どうすればよかったと思う?」と問いかけ、子どもに考えさせる。人間関係でトラブルがあったときも、親が解決するのではなく、「あなたならどうしたい?」と自分の意志を引き出す。こうした小さな経験の積み重ねが、子どもに「自分で決めていいんだ」という自立感を育てます。
同時に、社会全体が「子どもが失敗しても大丈夫」という寛容な空気を取り戻すことも大切です。学校でのミス、職場での失敗を“人格の欠陥”ではなく“成長の一部”と見なせる社会。そんな環境が整えば、親も過剰に不安を抱かずに済むでしょう。

■「親の安心」が、子の自立を支える
結局のところ、子どもが自立できるかどうかは、親がどれだけ“安心”できているかにかかっています。
親が「この子は大丈夫」と信じられないと、どうしても介入したくなる。逆に、親自身が人生の中で“他者との関わり”を楽しめている人は、子どもの挑戦も温かく見守れるものです。
ですから、子どもの自立を促す第一歩は、親自身が「自分の生き方に安心しているか」を見つめ直すことかもしれません。自分の不安に気づき、それを言葉にして他者と共有できる親ほど、子どもに過剰な期待や心配を押しつけずに済みます。
「守ること」から「信じること」へ。
それは、愛情の形を変えるようでいて、実はより深い愛の表現でもあります。
子どもを不安から守るのではなく、不安に立ち向かう力を信じて見送る——それが本当の“親の役目”ではないでしょうか。

■おわりに ― 社会で育てる「自立の文化」
親の不安が子を縛る社会は、やがて“挑戦を恐れる国”になります。
誰もが安全で確実な道を歩こうとすれば、新しい発想やリーダーシップは生まれません。
私たちはもう一度、「失敗しても立ち上がれる社会とは何か」「他者と関わることの意味とは何か」を、家庭だけでなく社会全体で考え直す必要があります。
学校教育、職場文化、地域活動——それぞれの場で“自立を促す仕組み”を育てていくことが、過保護社会の副作用を乗り越える唯一の道でしょう。

そしてその出発点は、家庭にあります。
親が安心し、子どもを信じ、社会がその成長を受け止める。
そんな循環が生まれたとき、ようやく「やさしさ」と「自立」が調和した社会が実現するのではないでしょうか。

