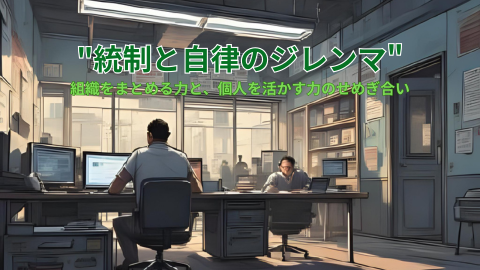
― 組織をまとめる力と、個人を活かす力のせめぎ合い ―
組織を運営していく上で、必ず直面する課題のひとつに「統制と自律のジレンマ」があります。統制とは、ルールや規律を設け、一定の方向へ組織を導いていくことを意味します。一方の自律は、個々のメンバーが自ら考え、裁量を持ちながら行動する自由を保障することです。どちらも組織にとって欠かせない要素である一方、その両立は決して容易ではありません。統制を強めれば自律性は損なわれ、自由を尊重すれば統一性は失われやすい。このせめぎ合いこそが、多くの組織が抱える「ジレンマ」なのです。

1.統制の必要性とその功罪
まず、統制の役割について考えてみましょう。統制は、組織に「一貫性」と「秩序」をもたらします。例えば大企業であれば、全国や海外に散らばる拠点が共通の基準で仕事を進めなければ、品質やサービスにばらつきが生じてしまいます。医療や製造業などでは、統制は安全性を守るために不可欠です。もし現場ごとにルールが異なり、個人の判断で好き勝手に行動してしまえば、重大な事故につながる危険性もあります。
しかし、統制が強くなりすぎると別の問題が浮かび上がります。それは「人のモチベーションを奪う」という側面です。細かい規則やマニュアルに縛られることで、自分で考える余地がなくなり、「どうせ決められた通りにやるしかない」と感じてしまう人も少なくありません。特に創造性や柔軟性が求められる業務では、過剰な統制は逆効果になり得ます。

2.自律の魅力とその落とし穴
一方で、自律には大きな魅力があります。自ら判断し、責任を持って行動する自由が与えられると、人はやる気を高めやすくなります。心理学でいう「自己決定理論」にも示されているように、人間は自分で選び取っていると感じる時に最も強いモチベーションを発揮するのです。
また、自律は現場の知恵を引き出す効果もあります。経営陣が机上で考える方針よりも、現場で働く人が直接感じる課題のほうがリアルで実効性のある場合は多々あります。現場に裁量を与えることで、変化の激しい時代に素早く対応できるという利点もあるでしょう。
しかし、自律を強調しすぎると、組織の方向性が散漫になる危険もあります。部門ごとに異なる判断を下すようになれば、顧客から見たときのサービスの一貫性が失われ、ブランドイメージを損ねる可能性があります。また、責任の所在が曖昧になり、「結局誰が決めるのか」という混乱を招くケースもあります。

3.現代におけるジレンマの深まり
この「統制と自律のジレンマ」は、現代社会においてますます複雑化しています。理由の一つは、働き方の多様化です。リモートワークが普及したことで、従業員が物理的に一か所に集まらなくても業務が進むようになりました。しかしそれは同時に、統制をどう働かせるかという新しい課題を生み出しました。
在宅勤務の社員に対して、従来のように「目で見て管理する」ことは難しくなります。だからといって監視ソフトなどで行動を細かくチェックすれば、不信感を招きます。自由度を認める一方で、成果をどう評価し、組織全体の方向性とどう整合させるか。まさにジレンマが浮き彫りになっているのです。
さらに、若い世代ほど「自律性」を強く求める傾向があります。「なぜそのルールが必要なのか」「なぜその方法でなければならないのか」と問い直し、自分の納得感を重視する姿勢が顕著です。従来のようなトップダウン型の統制も私は必要かと思いますが、それだけでは、彼らの心を動かすことは難しくなっているのです。

4.ジレンマを乗り越えるための視点
では、この難題にどう向き合えば良いのでしょうか。完全な答えは存在しませんが、いくつかの有効な視点があります。
(1)「目的」から逆算する
統制と自律の最適なバランスは、組織の「目的」によって変わります。安全性を最優先する医療や航空業界では統制が強くなければなりません。一方、クリエイティブな発想を求められるデザインや研究開発の現場では、むしろ自律性が重視されるべきです。つまり、「何を守るために統制が必要か」「どんな価値を生むために自律を尊重するか」を明確にすることが出発点になります。
(2)「ルールと原則」を分ける
細かいルールで縛るのではなく、大枠の「原則」を共有するという考え方も有効です。例えば「顧客第一」「安全最優先」といった原則さえ守られていれば、現場の判断は尊重する。こうした姿勢は、統制と自律を両立させる上での柔軟な枠組みとなります。

(3)「対話」による合意形成
統制と自律のジレンマを和らげるためには、双方向のコミュニケーションが不可欠です。上から一方的にルールを押し付けるのではなく、その背景や目的を現場と共有し、納得感を育むことが求められます。逆に、現場の意見を吸い上げ、ルールに反映させていくことも重要です。
(4)「柔軟な裁量権」の設計
全ての場面で一律に統制を効かせるのではなく、業務の特性や人材の成熟度に応じて裁量権を調整する方法もあります。新人には一定の統制を強め、経験を積んだメンバーには自律を拡大する。こうした段階的な設計は、組織の成長と個人の成長を両立させやすくします。

5.実例から見る統制と自律のバランス
実際の企業事例を見てみましょう。あるIT企業では、かつて厳格なルールを敷きすぎたことで社員の離職率が高まりました。「こんなに縛られては、自分の力を発揮できない」と感じる人が増えたのです。そこで経営陣はルールを大胆に削減し、「週の成果をチームで共有する」という原則だけを残しました。その結果、社員が自律的に工夫するようになり、むしろ生産性は向上しました。
一方で、自由度を過度に認めたベンチャー企業では、部門ごとにバラバラな方針で動くようになり、顧客への対応が不統一になってしまいました。その結果、信頼を失い業績が低下した例もあります。後に、最低限の統制を整備することで立て直しに成功しました。
このように、統制と自律の適切なバランスは、状況によって変わるのです。

6.そして ― 組織は「揺れ」を抱えて進む
統制と自律のジレンマは、どちらか一方を選べば解決するものではありません。むしろ常に揺れ動きながら、その時々の状況に応じて調整していく営みだと言えます。
組織に必要なのは、「統制か自律か」という二者択一ではなく、「どの場面で統制を強め、どの場面で自律を広げるか」を見極める柔軟性です。そしてその判断を支えるのは、最終的には「人をどう信じるか」というリーダーシップの姿勢に他なりません。
ルールで縛ることは簡単ですが、人の可能性を伸ばすには信頼が不可欠です。一方で、信頼だけに頼りすぎれば組織の足並みは乱れます。この矛盾を抱えながら、試行錯誤を繰り返すことこそが、健全な組織の成長につながるのではないでしょうか。
